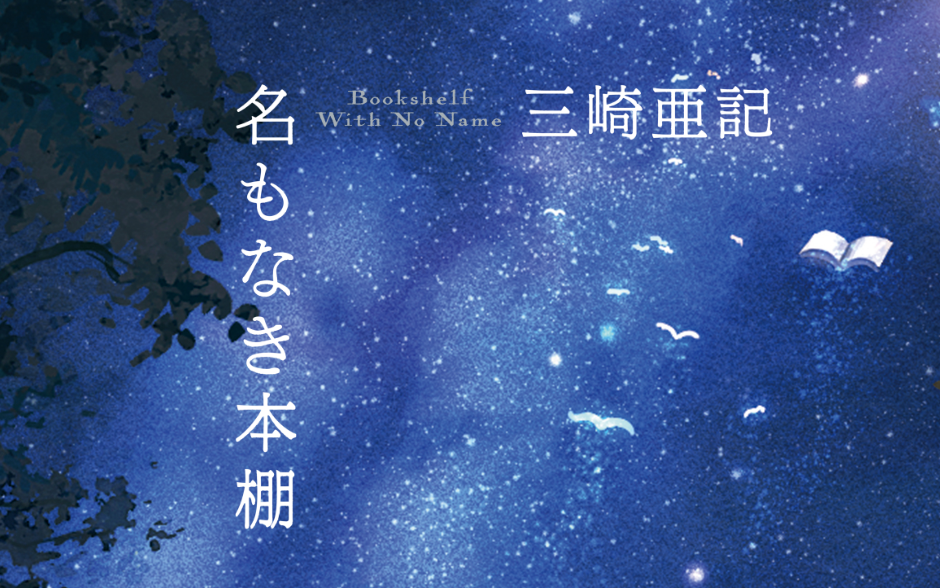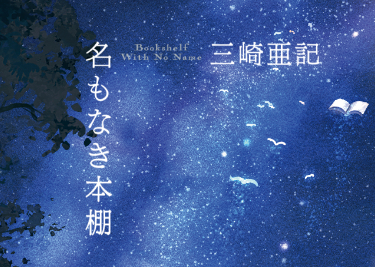- 中学・高校の教科書に採用された「私」「ゴール」「公園」も収録!想像を超える驚きに満ちた傑作掌編集。
- デパートのショーウィンドウの中で暮らす一人の女性。いつしか僕は、そのディスプレイの前で時間を過ごすのが日課になり……。(「スノードーム」)ゴミ集積所に座り込むサラリーマン。回収日ではない日に捨てられたその男は、近所の主婦には迷惑な存在でしかなく……。(「回収」)五分後には、あなたの日常が足元から揺らぎだす! 幻想、シュール、不条理、感動。刺激的な読書体験を約束する全19編。
書名:名もなき本棚
著者名:三崎亜記
2022年7月20日発売
定価:本体638円(税込)
カバーデザイン:高橋健二(テラエンジン)
イラストレーション:ぽち
ISBN:978-4-08-744413-1