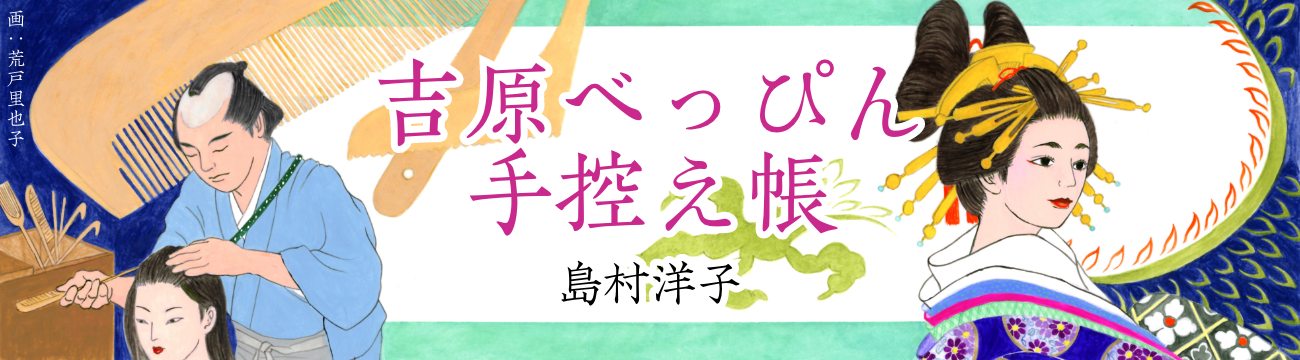第一話 金泥の櫛(くし)
島村洋子Yoko Shimamura
二
七日前に櫛をなくした。
櫛といっても髪をとかす実用のものではない。
笄(こうがい)と一対になった黒い漆塗りの豪華なものである。
お美弥は何度も何度も頭頂に手を当てて、そこにあるはずだった櫛の位置を確かめた。
客が居た時間にはあったはずだと思うのに、気がついたのはずいぶんたったあとである。
いまいる店に代々伝わってきたという値打ちのあるもので、これと見込まれた女郎に店主から預けられることになっている。
それでなくても毎日の売り上げから住み込み費用を差し引かれているのだ。
布団代、飲み食い、衣裳(いしょう)代と天引きされた挙句、親の借金は返すどころか金利がかさんで増えていく。
おまけに預かりものをなくしたとなれば、もはや何のために毎日生きているのかわからなくなる。
不安な気持ちでいっぱいだが、誰と言って相談できる相手もいないのが女郎商売のつらいところである。
小さな窓から外を眺めて息をつきながら、失(う)せ物を発見するのが得意と噂の八卦見(はっけみ)の先生のところにでも行こうかと思ったりもしたが決心がつかない。
櫛と対の笄はここにある。
黒の漆に金泥で小さな菊の花が何輪も描かれていて美しい。
お美弥は位の高い女郎ではないので、客からしげしげと装飾品を眺められることもなかったが、それでも自分なりには美しいものを集めたいと思っていた。
だから店主の春日屋幸兵衛(かすがやこうべえ)にそれを渡されたときは嬉(うれ)しく誇らしく思い、大切に扱ってきたのにまさかなくしてしまうなんて。
とりあえずなくしたことだけは白状しておいたほうが良いかと廊下を行きつ戻りつうろうろしていると、
「どうしたお美弥。腹でも下したのかい」
と女将に心配される始末である。
厠(かわや)でなくすこともないだろうし、盥(たらい)で足を洗う時にうつむいて落としたとしても気がつくはずだ。
お美弥はもともと気のつかないたちではない。どちらかと言えば気のつきすぎるきらいがあるくらいだ。
大切にしているものをうっかりどこかに置いて忘れてしまうということは自分でも考えられないのだ。
よしんばどこかに櫛を落とそうにもそこは悲しい籠の鳥の身、たいした範囲を動いてはいないのだから。
父親さえ博奕(ばくち)にのめりこまなければ、今頃は大工の棟梁(とうりょう)のひとり娘としてそこそこの暮らしはできたろう。
「正直ほど良いことはないんだよ。正直でいることが人としていっとう大事なことなんだよ」
別れ際にそう言って泣いていた母の言葉は忘れていないお美弥だったが、正直もなにも貧乏で娘を売るくらいなら嘘(うそ)つきのほうがずっとましだと思う。
それでも預かりものをなくしたことは言わねばなるまい。
しかし店主の幸兵衛の姿を見るたびにお美弥の喉は何かにふさがれたように声が出なくなるのである。
預かりものをなくしたのもつらいが、
「おまえと見込んでこれをつけてもらいたいんだよ」と言ってくれたその心を裏切ったように思えて申し訳ないのだ。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。