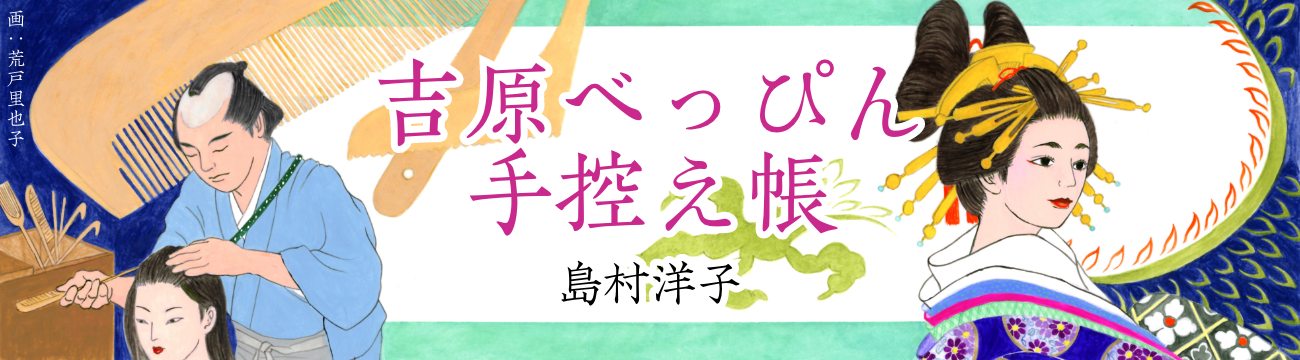第一話 金泥の櫛(くし)
島村洋子Yoko Shimamura
春日屋は吉原の大店(おおだな)中の大店で、店主の姿を見ない日などいくらもあるのだが、なぜかそんな日のほうがほっとするお美弥だった。
いろいろ知恵をめぐらせてみたのだが、相談ができそうなのは年に何度か出かけることができる髪結処亀屋のおしのばあだけである。
給金もほとんどない格も高くないお美弥はおしのばあが花魁(おいらん)たちの髪を結いにやってくる時についでに少し撫(な)で付けてもらう程度なのだが、それでも商売柄かおしのばあは聞き上手だった。
知恵を借りに来る女郎はたくさんいるはずだが、口がかたくて頼りになるおしのばあをお美弥は信用して相談しようかと考えた。
風呂でたまに髪を洗ってもいい時がある。
その「たま」のもっと「たま」の「たま」に髪結いに行ける日がある。
まあ誰かに心を開いてみたら、「なんだ、そんなことか。俺が一緒に謝ってやる。なんなら櫛も弁償してやる」などと言ってくれそうな馴染みの客の心当たりもないではなかったが、そんな借りを作ってそれでなくても縛られているこの身をこれ以上がんじがらめにしたくはない。
いったいどうすればいいかと迷いながら顔を上げると、店の外では人びとがあちこちで小さな輪を作って声高に話している様子である。
聞くとはなしに聞いているとどうやら男の溺死体が上がったらしい。
そんなことなら珍しいことではないのだが、瓦版を読み上げたとみえる男の言葉にお美弥は飛び上がった。
「なんでもその野郎の懐に黒い漆に金泥の菊の花の櫛が入っていてよう、なんかわけありらしいよ」
もしかしてとお美弥は慌てて外に出てあばたのあるその若い男に近づいていった。
「それ、見せてください」
字は読めなかったが、死人の似顔絵の横に忘れもしない櫛の絵があった。
男の顔に見覚えはなかったけれど、土左衛門の顔などどれも同じに見えるのかもしれないとお美弥は思った。
自分はこの男と同衾(どうきん)したことがあるのだろうか。
よく思い出せなかったが、いま大事なのはそんなことよりも櫛である。
なくしたことが露見するのも困るが、それより困るのはこの男を殺したのが自分だと思われることである。
殺しの下手人が市中を引き回されるのを子ども時分に見たことがあるお美弥は震え上がった。
これは誰にも話さないほうがいいと思い直し、それから幾日かを黙って過ごした。
髪には似たような櫛を挿しておいたので気づかれまいと思ったが、店主の幸兵衛にはわかるかもしれない。
お歯黒どぶに酔った客が転落するのはよくあることで、目立った傷もない男の死など皆がいつまでも覚えているものでもないと思うが、やはり恐ろしくて仕方がない。
苦界で生きている己が身だが、牢屋(ろうや)に入ることまでは思ってもみなかったのでお美弥は震えた。
櫛がなくなったことに気づいた瞬間から恐ろしかったが、いまはその恐ろしさの大きさも深さも変わってしまっていた。
とにかくなんとかしなくては、とお美弥はその「なんとか」もわからぬまま息をついた。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。