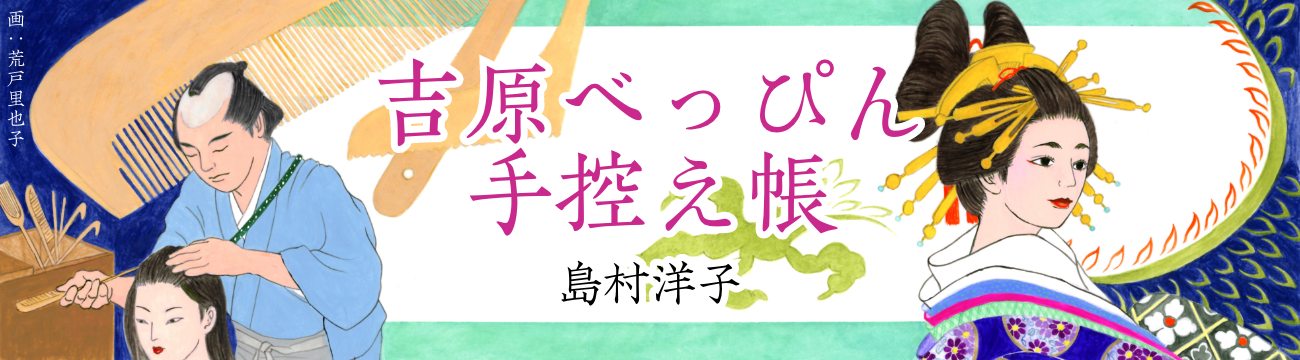第一話 金泥の櫛(くし)
島村洋子Yoko Shimamura
三
清吉が髪結いになったのは、親がいなかったからである。
育ててくれた鍛冶屋(かじや)の夫婦には子どもがなく、普通の暮らしをさせてもらったが、相次いで胸の病で若くして亡くなってしまい、髪結処に預けられることになった。
のほほんとさせてもらえるわけもなく下働きで一日が暮れ、ばたばたと過ぎた子ども時代の記憶は定かではなかったが、ただ夕暮れ時分が切なかったのは覚えている。
親のある子等が楽しそうに家路につくのを遠くに見ながら自分はいろんな年頃の見習い職人たちに交じって片付けをするのだが、この世に惨めなことは数あれど親のない身ほど惨めなものはないのだと思った。
そしていま頃、妹はどこでなにをしているのだろう、自分のように惨めな思いをしていないといいがと考えたりしていた。
そうこうして年月を重ねるうちに一人前の腕になった清吉は何軒か店を変わりながら妹を探し続けた。
髪を触られているうちに女は心をひらき、いろいろな噂を教えてくれるが、生まれ年とほくろだけでは土台、雲をつかむような話だった。
しかしこの世にはいろんなえにしもあるのに、わざわざ双子に生まれてきたということは深い意味があるのだろうと信じて清吉は髪結いを続けて来た。
清吉は玄人の女に人気があった。
話を親身に聞いてくれるし腕が良かったからなのかもしれない。
呼ばれて大店の女郎屋に行き、寝乱れた女郎たちの髪をさっさと撫で付けることもあったし、花魁たちの凝った頭を時間をかけて本格的に結うこともあった。
料理屋の女将たちの髷(まげ)を作ることもあったし、時間さえあえば髪結処亀屋に来た客をおしのばあと一緒に結うこともあった。
湯島からこの吉原にやってきてまだ日が浅い清吉であったが、その腕でめきめきと頭角を現していた。
その日はお得意を三軒ほど回ることになっていたが思ったより早目に仕事が終わり亀屋に戻るとお客が来ていた。
それがこの店に自分が奉公に上がった初日に出会った若い女郎だと清吉はすぐに気がついた。
「もう、怖くて怖くて」
そう囁(ささや)くように言い終えたお美弥という女郎の口元を見て赤い紅が愛らしい、と清吉は思った。
なんでもお美弥は櫛をなくしてしまい困っているらしい。
それは店主の春日屋幸兵衛からの預かりものの高価なもので大切にしていたのだという。
しかももしかしたらあの土左衛門が持っていたものがそれかもしれないと怯(おび)えているのだ。
もちろんお美弥はその男と会ったこともないという。
全く不思議な話である。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。