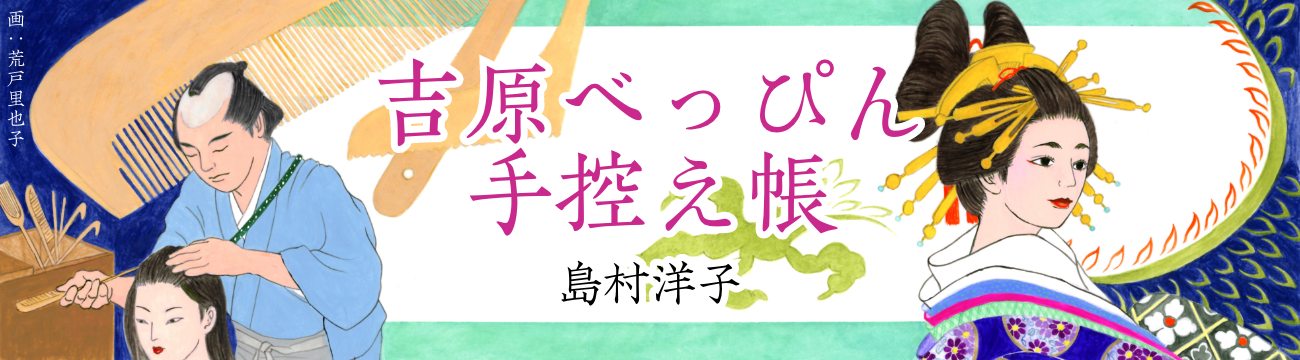第一話 金泥の櫛(くし)
島村洋子Yoko Shimamura
「こんなものはお好きかえ?」
龍田川が運ばせた熱々のものは小さな鍋だった。
黒い鉄の鍋の中には小さな丸い魚がびっしりと寝そべっていた。
その上にはみじん切りの白いネギがどっさりと載せられている。
「あ、どじょう!」
お美弥は思わず声を上げた。
小さな頃、近所の老人が桶(おけ)に丸っこい魚をたくさん入れて歩いていたのを見たことがある。
何かと尋ねてみたら、どじょうという生きものらしい。
「これを飼うの?」と聞いたら老人は笑いながら、「食い物だよ」と返事をされて驚いた記憶がある。
もうこの吉原を一生出られない身になってしまうと、幼い日の記憶は他愛(たわい)のないことでもぴかぴかに光って思い出される。
爾来(じらい)、お美弥は「どじょう」が食べ物だと知ってはいたが機会に恵まれず、一度は食べたいと思っていたのである。
甘いのだろうかしょっぱいのだろうか、ぬるぬるして気持ち悪くはないのだろうかといろいろ想像してみたことはあったのだが、判然としなかった。
「見た目はこんなだけど、おいしいんだよ」
そう言いながら微笑む龍田川の顔はまだ少女のようにお美弥には見えた。
「熱いうちにほら」
禿から渡された箸を手に取り、うながされるままお美弥はどじょう鍋を初めて食した。
なんとも言えぬ香ばしい匂いが漂っていた。
想像したのとは違ってぬるぬるしてはいなかったが。
醤油(しょうゆ)と砂糖の甘くてしょっぱい味とともに七味なのか山椒(さんしょう)なのかぴりりとした刺激もあって、お美弥は思わず、
「おいしい」
と言った。
龍田川はそれを嬉しそうに眺めていた。
相手を選べるという花魁とて所詮は商売である。
店のことも考えたらそんなに次々と選(え)り好みができるはずもない。
世間が考えているほどのわがまま放題が通用するわけもないのである。
楽しいことと言えばもっぱらうまいものを取り寄せることになってしまう。
そんな自分よりつらい身の上の女郎を見かけるとついつい世話をしたくなってしまう龍田川なのだった。
こうやって呑気(のんき)な時間を過ごしているようでも、もうすぐ花魁道中に出なくてはならない。
自分が買われる身であることはもとより、大店の看板でもあることの負担があったが、それはおくびにも出さない。
幼い禿の時から我が子のように育ててくれた春日屋幸兵衛への恩返しを龍田川はつねに考えていた。
「ぜんぶおあがり。なんならおかわりも持ってこさせるからね」
おかわりをもらうほどではなかったが、お美弥は父に食べさせてやりたいと思った。
借金まみれで何一つお美弥のためにはしてくれたことなどない父親だったけれど。
「こんなうまいものを食べても晴れない気持ちでいるんなら、なにかそうとうなことがあるんだね。よかったら話してみやんせ」
お美弥がごちそうさまでした、と言った言葉にかぶせるように、龍田川が言った。
この人はなんでもお見通しなのだなとお美弥は驚いた。
「じつは」
お美弥は重い口をようやくひらいた。
きっとこの人も春日屋の店主に櫛を与えられたことがあったに違いない。
だからここまで出世したのだろうと思いながら。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。