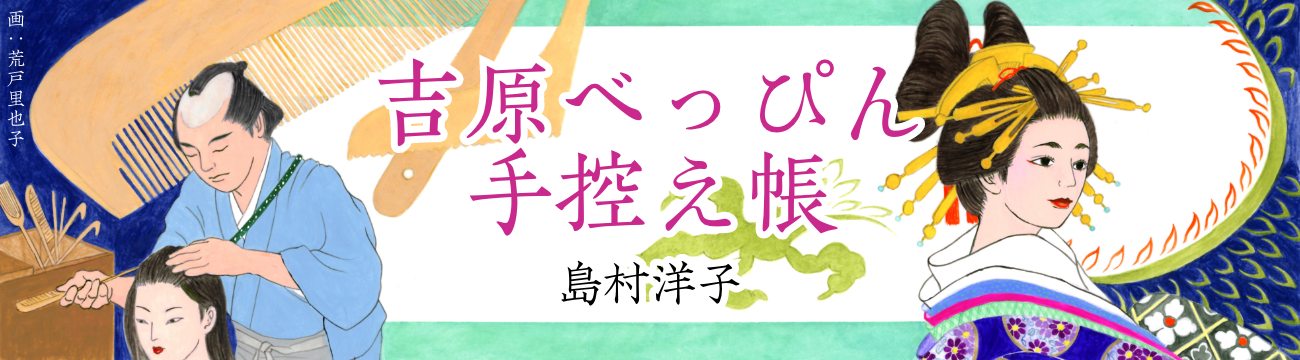第一話 金泥の櫛(くし)
島村洋子Yoko Shimamura
九
清吉が吉原の外に出るのは十日に一度くらいのことである。
女郎が好むであろうそれほど高価ではない簪や櫛を小間物屋から仕入れたり、鬢付(びんつ)け油を買ったり、息抜きにひとりで蕎麦(そば)屋に入ってみたりなにかとすることがある。
この日はおしのばあに頼まれた椿油を買いに日本橋(にほんばし)のほうに出てきた。
吉原の土手や田んぼのあたりとは違い、さすが日本橋はいろいろな店がたくさん並んでいて目移りするほどの品物があふれていた。
鬢付け油屋は華やかな表通りから何本も入った道具屋が並んでいる地味な通りにあった。
揚屋町(あげやまち)と呼ばれる吉原内部の商店街に行けばそれなりのものがあるにはあったが、やはり玄人が満足するものは日本橋まで来ないと見つからない。
椿油もそれぞれ香りや独特の手触りがあって清吉にもこだわりがあった。
「いつものを五合で」
そう注文するとすっかり顔馴染みとなった番頭が奥から出てきて挨拶した。
そして清吉に近寄って囁くように言った。
「亀屋さん、この前の瓶、まだお持ちですか」
「ああ、半分ほど使ったけどまだあるよ」
と言う清吉の言葉に歯の出た番頭は言いにくそうに切り出した。
「お代はお戻しいたしますから、その瓶をお返し願えますか」
「え、またそりゃどうして」
使ってみたところいつもとなにも変わらなかったのだが、と清吉は続けた。
「いえ、そう言っていただけるとありがたいんですが、うちの新入りが調合を間違えたらしく微妙に種の量が少なかったんです。お気づきになる方はいらっしゃらなかったのですが、やはり手前どもも長い間の商いで看板に傷がつくようなことはできませんもんで。いえ今回のお代は結構ですから、前回のそれをいつでもいいからお戻しいただくというお約束をいただきまして、今回のことはご内密にということでよろしくお願いします」
べつに言わなければわからないことだろうに本当に丁寧なことだな、と思いながら清吉は堤を歩いていた。
しかしそれが商いという道の厳しさなのだろう。
今回の件に気づいている者があったとしても噂を封じ込めることができるし、なんならこのことを奇貨として事後の対応が見事だと逆に評判になるかもしれない。
どの道でも進んでいくのは気を使い大変なことだ、自分も髪結いとしてふんどしの紐(ひも)を締め直さねば、と清吉は思い、もしやと気づいた。
なくなった二つの櫛のことである。
あんな偽物が世の中に出回るのが許せないと思った人間がどこかにいて、それを集めているとしたらどうなのだろうかと。
そんな気もするが全くの見当違いのようにも思えて清吉は空を振り仰いだ。
吉原の中ならどこでも人が出入りできるので、物がなくなったの盗られたのは日常茶飯事である。
翡翠(ひすい)の帯留がないの象牙(ぞうげ)の三味線のバチがないの、着物が見当たらないのはしょっちゅうで女郎同士がつかみ合いの喧嘩をしているなんてことはとくに珍しいことでもない。
とはいえ金や高価なものが盗まれることはあっても、人の頭に挿されたものをわざわざ盗むというのはなかなか大変なことである。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。