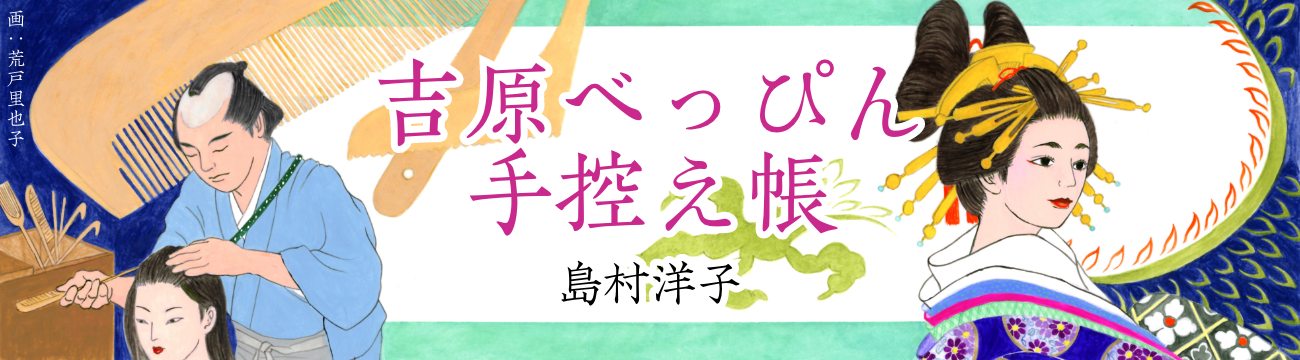第一話 金泥の櫛(くし)
島村洋子Yoko Shimamura
十五
そういえばあれからぱったり来なくなった客がいる。
髪を清吉に結ってもらいながらお美弥はあることを思い出した。
瓦版を眺めながら気になったことがあった。
もしかしてあの土左衛門は急に来なくなったその男ではないのか。
来なくなる男は季節ごとに数人あって、あれどうしたと思っているうちに突然やって来たりもするからこの商売はわからないのだが、時がたつにつれて土左衛門はその男だろうという確信が日に日に強くなって来た。
男の本当の名前はわからないが春日屋では「よしさん」と呼ばれていた。
夜伽の時に世間話はするが、布団の中で女郎に聞かせる話が真実ではないのはお美弥にもわかっている。
そのよしさんの見てくれは中肉中背、なんというくせもない男だったが過去の流行り病のためか顔に目立つあばたがあった。
気の優しいたちで扱いやすかった、とお美弥には覚えがあった。
十日に一度はやって来ていたように思うのだがそういやぷっつりと姿を見せなくなった。
客は気まぐれなもので何かに腹をたてて急に来なくなることもあるのだが、最後に会った時に別段粗相もなかったと思うし、何が理由なのかはわからない。
帰り際に頭を下げるのだが、その時にあの櫛をよしさんがひょいと奪うなんてことが考えられるだろうか。
何度か通って来ているうちにどうやら本気になったらしく、いつかおまえを落籍して晴れて夫婦(めおと)になろうと言ってくれることもあったが、それこそそんな話は女郎と客のあいだでは千回も万回も交わされることである。
だからお美弥も、
「本当になるなら嬉しいです」
と返事はしておいた。
しかしこの吉原を自分の目の黒いうちに出られるなんて本気で考えているわけではなかった。
病にでもなって寝込んでいるのだろうか。
それとも商売がうまくいかなくなって、国にでも帰ってしまったのだろうか。
あるいは何か良くないことがあってもうよしさんはこの世の人ではないのだろうか、と思うとお美弥は気が気ではなかった。
こちらがわに惚れたという気持ちはなくても、得意客をひとり失ったというのは商売として痛くもあった。
よしさんがあの櫛を持っていったのだろうか。
「どこで何をしている人なのかはわからないんですが、とにかくそんな人がいるんです。よしさんとお呼びしていたんですが」
「よしさん?」
鸚鵡(おうむ)返しにそうつぶやくと清吉は気になることでもあるらしく宙を見つめた。
お美弥はよしさんが自分のことを好きなあまりにそうっと手を伸ばし、頭上の櫛を抜きとる姿を想像した。
それを懐に押し抱いたまま、川に身投げしたとしたらなんといたわしいことだろう。
暗いお歯黒どぶに男が身投げする情景が浮かんできたお美弥は涙がこぼれそうになった。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。