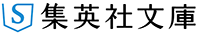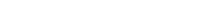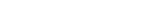思い込みというものは厄介だ。毎年夏に『ナツイチ』フェアを大展開している集英社文庫といえば、自分が生まれるずっと前から歴史を刻んできた大先輩のような存在だとばかり思い込んでいた。
ところが、この度の四十五周年企画で、集英社文庫が私と同じ一九七七年生まれであると知った。
「えっ? 同級生だったんですか? うん、昭和五十二年生まれ。そうだったんだ!」
といった具合で、急に親近感が湧いた。
そんな同級生・集英社文庫の中から、今回は『鉄道員』についてお話ししたい。
私が初めて『鉄道員』を読んだのは、有り余る時間を音楽と読書とバイトに費やしていた大学生の頃。まだ二十歳だった。浅田次郎さんが同作で直木賞を受賞された折に、単行本で読んだ。書店で、冒頭の表題作『鉄道員』の書き出しをちょっと立ち読みした途端にレジへ向かってしまうほどの、強烈な引力があった。
その後、映画『鉄道員』も観て深く感動した。表題作の印象があまりにも大きくなり、他の短編作の記憶を失いかけていた。
この度、二十四、五年の時を経て、集英社文庫で『鉄道員』を再読した。すると『鉄道員』の他の短編作の記憶が鮮やかに蘇(よみがえ)り、しかも初読とは全く異なる印象を伴った八つの短編集として胸に迫ってきた。
表題作『鉄道員』は、二十歳の頃とは別人になったような心地で、味わい深く読んだ。
舞台は雪深い正月の北海道で、廃線を三ヵ月後に控えたローカル線。主人公は、廃鉱になった旧炭鉱町の終着駅で一人、一両編成の気動車・キハ12形の到着を待ち、出発を送り出す老駅長・佐藤乙松。その実直な生き様に、胸を打たれた。過去に娘を生後二ヵ月で亡くし、妻にも先立たれた乙松だが、彼の矜持(きょうじ)が凝縮された一文がある。
〈ポッポヤはどんなときだって涙のかわりに笛を吹き、げんこのかわりに旗を振り、大声でわめくかわりに、喚呼の裏声を絞らなければならないのだった〉
大学生だった私は、乙松の仕事に対する姿勢に尊敬の念を抱き、物語の後半で乙松が受け取る哀しくも尊いギフトに純粋な感動を覚えた。ある意味、無責任な憧れを抱いた。
あれから社会人になり、職を転々とし、結婚して一人の娘の父親となり、四十五歳になった。
平日は勤め人として働き、土日に小説を書いている。
職場で困難に直面する度、あるいは原稿で行き詰まる度、私はすぐに弱音を吐いたり、頭を抱えたり、ため息をついたりする。涙の代わりに愚痴を言い、げんこの代わりに「そこをなんとか……」とすがりつき、大声でわめくかわりに「どうすりゃいいんだ……」と無力の独り言を呟(つぶや)く。私は乙松のような筋の通った人間にはなれない。
二十歳の頃とは全く違う読後感を抱き、表題作『鉄道員』を読み終えた。自分の弱さを省みた。一方で、不格好でも懸命に生きていればきっといいことがあるとも思えた。
続けて他の短編作も読み進めるにつれ、初読の時の記憶が次々と蘇ってきた。
八つの短編作のうち、今回の再読では『角筈にて』が最も心に染みた。四十六歳の中年商社マン・貫井恭一の物語。大学生の時分には読み流していた恭一の葛藤が、四十五歳の私には痛いほど胸に響く。
冒頭、一流商社でプロジェクト失敗の責任を負ってブラジルの支社へ転勤となる恭一の、壮行会の場面から始まる。出世街道からの脱落、左遷の片道切符だ。壮行会の帰り道、恭一は新宿の街で父親に似た人物を見かける。
物語は少年時代の場面にカットバックする。
母親を病気で亡くした八歳の恭一少年は、新宿・歌舞伎町界隈(かいわい)の、かつて「角筈(つのはず)」と呼ばれた一画のバス停で父親と生き別れる。置き去りにされたのだが、恭一少年は自分の身に起きたことを理解しつつも受け入れられないまま、角筈に近い淀橋(よどばし)にある伯父伯母の家で、その家の子供たちと一緒に育てられる。
父との別れ際に「しっかり勉強して、大きな会社に就職しなけりゃだめだよ」と言われ、その教えを守って東大に入り、一流商社に入った恭一。競争に敗れ、遠い海の彼方の赴任地に旅立つ直前、日本で過ごす最後の日に、恭一は三十八年間の呪縛から解き放たれる。四十六歳の恭一に幸あれと願いたくなるラストシーンだ。
巻末の北上次郎さんの解説によると、八つの短編作のうち、推す作品が人によってことごとく異なるという。
〈本作品集がリトマス試験紙であるというのは、読み手の年齢、性別、経験、環境、人生観などによって、このように感じ入る作品が異なるからである〉
二十歳の頃『鉄道員』派だった私は、四十五歳の今『角筈にて』派となった。人間の多面性を文章と行間に織り込んだ浅田次郎さんの筆致による、マジックだと思う。
同時に、文庫本の存在意義を改めて思い知った。文庫本は長い時を経てなお読み継がれ、残り続ける。本好きの人々に再読の機会と新たな気付きを与え、ライトな読者には読書への入口にもなる。
集英社文庫の四十五周年を心よりお祝い申し上げたい。偉大なる同級生に「お互い、よりよく年を取っていこう」とエールを送りたいと思う。