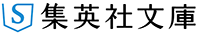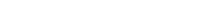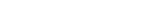僕は演劇をやっているので、らもさんのことは劇作家として知っていた。お会いしたことはなかったが、勝手に何か同じ村の住民のように親しみを感じていた。だから本屋でらもさんの著作を見つけた時は「ああ、らもさん小説も書いてるんだ」くらいに、思った。最初に手に取ったのは確か「超老伝―カポエラをする人」だったように思う。薄かったからだ、本の厚さが。当時も今も、集中力のない僕は、薄い本を好んで読むのだった。詳細については省くが、面白かった。途中で著者が投げやりになっている感じも含めて面白かった。
他に数冊読んで、薄いのはもうなくなって、「ガダラの豚」上中下巻が残った。どうしようかな。途中で投げ出しそうだな。カポエラをする人ですら、らもさん途中でやる気を失って、最後の方は投げやりな感じあったしな、上中下巻なんて、こっちも向こうも集中力が続かないんじゃないかな。
「でも」とか「しかし」とか続きそうな展開の文章でしょう? ネガティブな点を並べておいて、それを覆すことで、この本の良さを喧伝(けんでん)するつもりだと思いますでしょ? それがまさかの、その通りなんです。芸がなくて申し訳ないのだけど、「ガダラの豚」はほとんど3日かからずに読み終えてしまった。
あれが多分もう20年前で、それから数年に一回は読み返す。話の筋が面白いだけなら一回読めばそれで終わりだが、それ以外の何かがこの本にはある。その「それ以外の何か」をここに書くのが僕の仕事なんだろうけど、それが未(いま)だに判然としない。言えるのは、登場人物たちの魅力。テレビ業界の住人や、宗教家、手品師、学者、市井(しせい)の若者、無数の人物たちがそれぞれ一つの宝石のように印象に残り、そこにどす黒い石や、気味の悪い骨のかけらのような人物がちりばめられ、聞いたことのない国の博物館に迷い込んだような感覚である。
魔法と手品、奇跡とペテン、聖に対する邪の境界線が読み進めていくうちに、歪(ゆが)み互いに侵食しあい、そのあわいに読者は漂い、登場人物たちと一緒に恐怖に立ち向かい、最後はどうなるのでしょう? 読んでください。
ただの荒唐無稽ではなく、らもさんの偏執的な知識が土台になっているからか、妙なリアリティがあり、「いやいや作り話だから」と判っていながらも、ただ知らないだけで今もこのような出来事が、どこかすぐ近くで起きてるんじゃないかと思わせる。ああ、みんなに読んでもらいたい。友達が落ち込んでいる時や、何か面白いことない? っていう時にはまず最初にこの本を勧める。