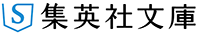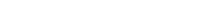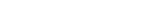小さい頃から人付き合いが苦手で、学校の休み時間も一人で本ばかり読んでいた。おかげで通知表にはしばしば「協調性を」と書かれたし、小学校卒業時、互いに送り合った寄せ書きには、「一人の方が楽なんて言っちゃダメだよ」とのクラスメイトからの一言がしたためられていた。
当時の私からすれば、それでも努力してかなり周囲に合わせていたつもりだったし、皆で何かすることが決して嫌いだったわけではない。ただそれよりも一人で読書する方が楽しかったのだ。
それだけに一人の時間を喜ぶ一方で、私は多くの人々が協力する物語にも強く心惹かれた。例えば『十五少年漂流記』、『ぼくらの七日間戦争』。個性的な人々がぶつかり合い、困難を乗り越える力に憧れ、しかし自分にはそんな団体行動は向いていないなとも寂しく思った。
『プリズンホテル』に出会ったのは、そんな自分の気性を冷静に観察できるようになった高校生時代。最初の感想が、「なんだ、これは」だったことを今でもよく覚えている。
なにせ登場人物の大半が、一般的な協調性とは致命的に程遠い。偏屈を通り越してほとんど人格破綻者である癖に、妙なところで幼子のごとき純粋さを見せる売れっ子小説家、その人ありと言われる侠客(きょうかく)でありながら、我が身の危機となると周囲が呆(あき)れるほど取り乱す医者嫌いの奥湯本あじさいホテルことプリズンホテルのオーナー、武闘派を絵に描いたような外見の純愛派若頭兼副支配人……全員、ひと癖どころではない癖があり、それでいてここぞというところではまっとうに人生を語り、恥ずかしいほど真剣にぶつかり合い、そして笑顔でプリズンホテルを去ってゆく。
ずるい。そして、うらやましい。こんなに協調性に欠けているのに、心の最も奧深くでつながり合える場所があるなんて。私もこのホテルの一員になりたいと、心の底から願い、そして気づいた。
プリズンホテルの人々は、別に団体行動をしようとは思っていないし、それを周囲に強いもしない。ただそれぞれが自分のなすべきことを果し、他人の個性を受け入れた時、彼らは個でありながら一つ処(ところ)に集う仲間となりえるのだ。
だとすればこの物語は決して、人々の和を描いたものではない。一樹の蔭(かげ)に宿り、一河の流れを汲(く)むことも前世からの因縁であるとの言葉があるが、本作はプリズンホテルという一樹の蔭に宿った人々――この世にたまたま隣り合わせた人々の縁の物語なのだ。
一度そう考えると、不思議に自分を取り巻く世間までがプリズンホテルの中のように見えてきた。京都の平凡な高校生でありながらも、心は上州(じょうしゅう)の名湯の奥座敷に生き、暴走族言葉の抜けないフロントマンや何事にも熱中しすぎるシェフ&おいしさのあまり口に入れた途端笑いが止まらなくなる料理を作る板長や元伝説のヒットマンのバーテンダーたちと在る気がした。そう、自分がプリズンホテルに生きられるかどうかは、己の心の持ちようただ一つ。だからわたしにとって本作は、この人生の過ごし方を教えてくれた大切な物語なのだ。
ちなみに数年前、北海道を一週間ほど旅行した折、あるホテルの小さな図書室に、本書がひと揃(そろ)い並べられていた。これも何かの縁だろうと部屋に借りてゆき、布団の中で楽しく読み返したが、今それがどこの宿だったかを思い起こそうとしても、なぜか不思議にその他の記憶がない。
はて、もしかしてあれは本物のプリズンホテルだったのか。だとすればもう一度、あの宿を訪れてみたいような、それは野暮なような。ならばせめて少しでも心だけでもあの慕わしいホテルに馳(は)せるべく、私はまた物語の中の好きな人々に会いに行く。