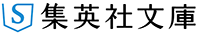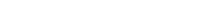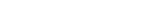時代は移り、ものごとはつねに変化する。
新しいなにかが、つぎの新しいなにかに置きかえられ、それもまた、つぎなる新しさの出現によって古くなる。時代とは、そういうものだ。そしてわたしたちは順番に歳を取り、いずれは表舞台から去ってゆく。
だが、たとえどんなに年齢をかさねたとしても、まさか自分が青春を送った日々が、のちに〈石器時代〉とよばれるようになろうとは、さすがに思いもしなかった。
今年で45周年を迎える集英社文庫、その歴史と同い年の私が二十代をすごした1990年代後半は、インターネットの世界では、〈石器時代〉に相当するそうだ。
そういう位置づけになるのも、いたしかたない。あの当時、インターネットはまだ使いものにならなかった。通信速度は遅く、静止画像でさえ表示に時間がかかった。それでも人々は、未来のインターネットの発展に希望を抱いていた。そこにはユートピア的なイメージがあって、現在のような、善も悪もなく、ただ圧倒的な量のデジタル情報が氾濫している、といったカオス的な状況は、ほとんど考えられていなかった。
これから紹介する『アド・バード』は、インターネットの〈石器時代〉よりも少し前に書き終えられ、そして若かったわたしが、夢中になったSF小説である。
〈アド・バード〉とは〈アドバタイジング・バード〉のことで、作中の近未来世界において、企業の宣伝広告のために人工的に改造された鳥だ。群れで消費者向けの文字を作り、あるいは話すこともできる。アド・バルーン、すなわち広告気球の鳥版と言えばわかりやすいような気もするが、しかしいまとなっては、デパートの上空に浮かぶアド・バルーンを見る機会はまずないだろう。かく言う私も、飛行船を使った広告なら見たことはあるが、気球をこの目で眺めた経験はない。
『アド・バード』の舞台となる近未来は、鳥のみならず、猿、樹木、そして多数の虫たちまでが、企業の広告戦争の道具として人工的に手を加えられ、異常な進化を遂げて暴走したあげく、ついには文明そのものを荒廃させてしまった世界である。生物だけではなく、機械もまた暴走し、際限のないコマーシャルで、都市の上空を埋めつくしている。
本文から引用しよう。それは、「午後になって雲が厚くなり、そこにまたさまざまな宣伝の映像が動き回っており、相変らずそれらの映像からすさまじい音と音楽が激しくまじりあって降りそそいでいたが、ずっと絶え間なく続いているので、永いこと外を歩いていると頭の中が麻痺し」てくるような空である。
『アド・バード』でえがかれた近未来のディストピアには、現在のわたしたちから見れば、二重のノスタルジーを抱かせる要素がある。一つは〈アド・バード〉という架空の名称の起源となったはずのアド・バルーンが、もはやどの都市にも浮かんでいないということ。
そしてもう一つは、先に引用した企業同士の終わりなき広告戦争が、都市の上空に投影されるのではなく、スマートフォンやタブレット型PCなどのデバイスをとおして、デジタル空間で日夜おこなわれているという、現在の現実との差異である。
未来は現在を軸にして想像されるのだとすれば、『アド・バード』はまさに想像力のその特質をあらわしている。90年代より以前、人類がインターネットのカオスにさらされる前、デジタルの闇が到来する前、あのころに夢みられたディストピアの世界は、そこがどれほど危険な場所であっても、現在のわたしたちの心に、なにか不思議な温かさをあたえてくれる。ソーシャルメディアでも、メタバースでもない、アナログ感覚を残した別の未来。
集英社文庫は2022年に45周年を迎えたが、つぎの45年後、2067年にふたたび『アド・バード』が読まれるとき、人々はなにを思うのだろうか。