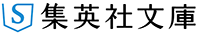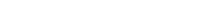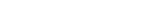物語は、原因不明の震え(という表現では生ぬるい。本人曰〈いわ〉く、セルフロデオマシーンになっているような感覚)に襲われた主人公・みのりが、生まれて初めて救急車で運ばれるシーンから始まる。昔の恋人の結婚を知ったショックから胃痛を発症した彼女が、病院で処方された胃薬を飲んだ途端、症状が始まったのだ。
あらゆる病院に落胆させられた彼女が出会ったのが漢方だ。担当の坂口医師に魅(ひ)かれている、という少々よこしまな理由もあるが、東洋医学そのものの魅力に、彼女は徐々にはまってゆく。例えば「病名はないのではなく、いらない」や、「自分の生み出す変化は自分の一部」だという坂口の言葉は、みのりだけではなく、私たちの心にも小さな波紋を作る。その波紋は確かな震え(ロデオマシーンのような乱暴なものでは決してない)となって、私たちを物語の渦中に引き込んでゆく。みのりが、自身の身体を、そして心を仔細(しさい)に見聞し、その中に世界を見る道程を、私たちも共に旅してゆくことになるのだ。
さて、みのりの身体も心も、とても疲弊している。だから、その道程は少々過酷なものになるはずだ。だが、著者のユーモアに溢(あふ)れた文章は、読者を突き放さない。どのページにも、「こういうことって誰にでもあるよねぇ」という、程よい諦めと大袈裟ではない希望と当たり前の肯定が適切に混じった、とても信頼できる温度がある。
その温度は、あらゆる登場人物たちも包む。ウツを患っている友人のサッちゃん、ロマンス欠乏症の志保さん、自由奔放な茜ちゃん、茜に魅了されている森ポン、酔って人に絡む日野、ロープ手品にハマっている大家さん。彼らは一様に完璧ではなく、中にはちょっと、本格的にムカつく奴もいるが、著者はやはり、その誰にも平等な視線を注いでいる。人間はそもそも複雑で厄介だ、という前提から始めていることが、その視線を確かなものにしているのだろう。
それは身体のそれぞれを独立した器官として捉えるのではなく、混じり合い、連結し合った、やはり複雑な有機体として捉える漢方の考え方に似ているのではないか。
つまり、この小説の在り方そのものが、漢方の在り方に似ているのだ。人間が人間として生きてゆく以上、決して避けることの出来ない不和や不調、喪失や寂しさ、そして優しさについて書かれたこの小説は、じわじわと私たちの感性を内側から揺り起こす魅力に満ちている。
発売から十数年経ったこの小説を、私がふとした瞬間に何度も読み返してしまうのも、そのせいだ。読むたびに、私は自身の身体を、心を愛しく思う。きっとこれからも、長くお世話になるだろう。