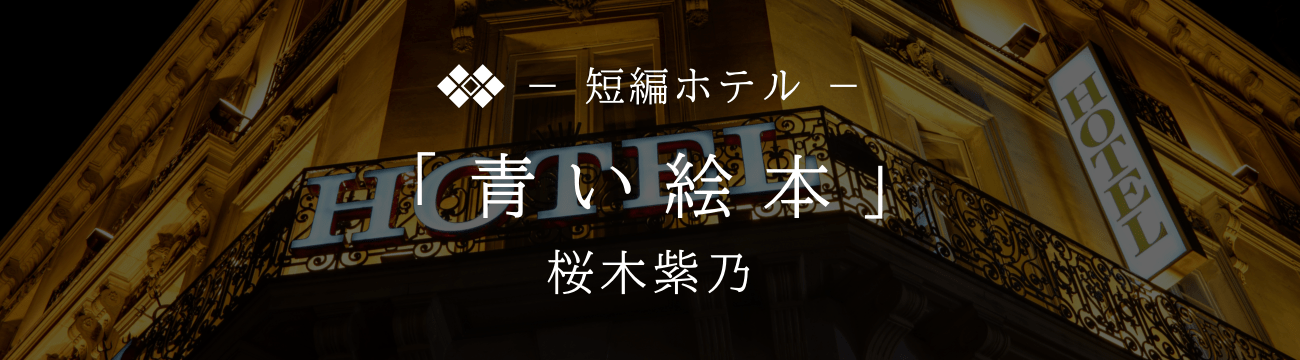青い絵本
桜木紫乃Shino Sakuragi
『ミヤちゃん
元気にしてますか、好子です。そちらは寒さも極まっているころでしょうか。今日はお誘いのメールです』
なにかと思えば、北海道の温泉に行きたいという。
好子からの簡潔なメールを一行一行目で追っていると、唐突に「絵本を書きたい」とあった。
『今回の絵本は、五年も空いてしまって、シリーズも途絶えているので、変化するいいチャンスのような気がするの。少しぼんやりしたいので、北海道に行きます。たまには、わたしに付き合ってくださいな。いい温泉宿を紹介してもらったので、二泊三日、わたしに時間をちょうだい』
候補日がふたつあった。月末の三日間なら依頼のあった背景が仕上がっているころだろう。久しぶりに会う好子と、温泉で語らいながら─そこまで考えて、遅まきながらメールの内容が頭に入ってくる。
少しぼんやりしたいので─
絵本作家として一時代築いた「たかしろこうこ」が、ぼんやりしたいとはどういうことだろう。
室温が下がってきたのか、少し寒い。着る毛布を羽織って、もう一度読み返してから返信画面を開いた。
『好子さん、こんばんは。こちら、毎日雪がちらついていますが、ご想像どおり静かな毎日です。温泉? 好子さんから温泉に誘われたの、何十年ぶりだろう。二泊、OK。後者の日程だと、背景も仕上げも終わってる頃です。飛行機が決まったら、教えてね。空港までお迎えに上がります。あ、どこの温泉でしょう。来るまで内緒ですか?』
母と娘ではなくなってからのほうが、好子の天真爛漫(らんまん)な性分が露(あら)わになった。ふたりとも、父のそばにいるときはどこか遠慮と束縛が絡み合った空気の中にいたのだ。
送信する一瞬前、美弥子の脳裏に自分はどうだったのかという思いが過ったが、好子のメールが前に出て来た途端、それも流れた。
月末の三日間、それまでには美弥子の描いた背景に漫画家が人物を入れてくるだろう。仕上げまで入れても─終わる。なにか、愉快な気持ちが美弥子を包んだ。自分たちは本来、曜日で生活するような人間ではなかったことが思い出された。
これが終わったら、甘いものを食べに行こう。これが終わったら、ゆっくりしよう。これが終わったら、温泉に浸かろう。休みを設定するのは自分で、その休みも自ら取りにいかねば手に入らぬものだった。
ああ、とひとり頷(うなず)いた。
基準は父だった。人生塾に集ってきた若者の時間を農作業と説教と稽古で埋めた王は、彼らのいったい何が欲しかったんだろう。無休と無報酬は無農薬と無添加という言葉に変換されたが、王は決してそれらを自分の口に入れなかった。
去ってゆく若者の口から、刑務所という言葉が飛び出したとき、暖房もろくにない宿泊施設は内側から大きな球体になって、緩やかな坂を転がり始めた。内紛も解散も、美弥子は父が迎えた王国の終焉(しゅうえん)を、新聞とテレビのニュースで知ったのだった。
洗脳という言葉も飛び交った「北国の王様」にまつわる記事は、いっとき週刊誌に取り上げられもしたが、北海道のちいさな話題で、誰が得をしたり損をしたりという話題でもなかったため告発もコメントもどこか牧歌的で、話題性も長続きはせず今は静かだ。
生まれながらに染みついた曜日感覚は学校に通っていたころも同じで、どちらにも居場所のない生活は、美弥子の内側から「対話」を奪った。言語化できるようになったのは、つい最近だ。
年を取るということは、言葉を得るということでもあるのだろう。たいがいのことは、言葉で納得できるし、言葉になる。だから─言葉にしないことも覚えたのだった。
- プロフィール
-
桜木紫乃(さくらぎ・しの) 1965年北海道生まれ。2002年「雪虫」で第82回オール讀物新人賞を受賞。07年同作を収録した単行本『氷平線』でデビュー。13年『ラブレス』で第19回島清恋愛文学賞、同年『ホテルローヤル』で第149回直木賞、20年『家族じまい』で第15回中央公論文芸賞を受賞。他の著書に、『硝子の葦』『起終点(ターミナル)』『裸の華』『緋の河』など。近刊に『俺と師匠とブルーボーイとストリッパー』がある。