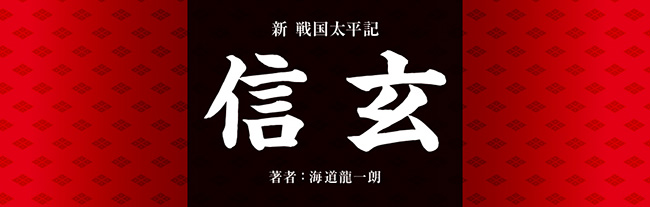第三章 出師挫折(すいしざせつ)
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
この後、しばらく内政についての評議が続けられ、家臣たちも豁達(かったつ)に意見を述べた。
――なんと実りの多い評定であろうか。信虎様の御顔色を窺(うかが)うばかりの評定では、とうていあり得なかった状況だ。皆が家臣としての自覚を高め、良い流れができてきた。
信方は満足げに一同の様子を見渡してから次の議題に移る。
「それでは最後に懸念のひとつとなっている佐久(さく)の件について話し合いたいと思う。これに関しては……ええと、伊賀守(いがのかみ)、そなたから現況を報告してくれ」
「承知いたしました」
跡部(あとべ)信秋(のぶあき)が話を引き取る。
「実は今、佐久と小県(ちいさがた)において由々しき事態が起こっておりまする。当家の代替わりに乗じ、箕輪(みのわ)城主の長野(ながの)業正(なりまさ)が佐久へ出張ってまいりまして、大井(おおい)、平賀(ひらが)、志賀(しが)らの残党が戦わずして降伏いたしました。皆様もご存じの通り、それは前の海野平(うんのだいら)合戦に端を発しておりまして、長野業正の背後には関東管領職(かんとうかんれいしき)の山内上杉(やまのうちうえすぎ)憲政(のりまさ)殿がいることは明白にござりまする。そこで、それがしが内実を探るために諜知(ちょうち)を行いましたところ、意外な事柄が発覚いたしました。少し長い話になりますが、どうか最後までお聞きくだされ」
信秋が言ったように、箕輪城主の長野業正は山内上杉憲政の重臣であり、上野(こうずけ)で最強と噂される剛将だった。
そして、憲政が出兵を決めたのは、武田と村上(むらかみ)の連合軍に小県を追われた海野棟綱(むねつな)の懇願があったからである。
信繁の初陣となった海野平合戦での敗北により、海野棟綱と滋野(しげの)一統は岩櫃(いわびつ)城へ逃げ込み、そこから上野平井(ひらい)城の関東管領に援軍を願った。
当初は信虎との同盟関係から上杉憲政は出陣を渋っていたが、突然、武田家の代替わりが強行されたことを知り、これ幸いと佐久への出陣を命じた。
長野業正が総大将となって佐久へ出張ったのだが、武田に滅ぼされた平賀玄心(げんしん)の残党が戦わずして下り、長野勢は芦田(あしだ)郷(北佐久郡立科〈たてしな〉)を荒らしただけで海野の旧領である小県郡へは攻め入らずに帰還してしまった。
そこには裏の取引があった。
「それがしが調べましたところ、長野業正は海野棟綱のために屈強な村上義清(よしきよ)の軍勢と戦うことを良しとしておらず、諏訪(すわ)頼重(よりしげ)と和談を行い、帰還したと思われまする。なんのことはない、関東管領殿の面目だけを立て、自陣営にまったく損害が出ぬうちに兵を引いたのでありましょう。問題は、当家に無断で勝手に和睦を進めた諏訪頼重にござりまする。しかも、長野業正が下した平賀の残党がすべて諏訪家の麾下(きか)に入ったと聞いておりまする。これは当家に対する明らかな盟約違反だと思いまするが」
跡部信秋は憮然(ぶぜん)とした面持ちで言う。
「そのことについては、それがしも同じことを聞きました」
海ノ口(うんのくち)城の守りを預かっていた原虎胤(とらたね)が発言する。
「どうやら、村上義清と長野業正は内々に通じていたらしく、小県で争わぬという約束で村上が佐久への出兵に眼を瞑(つぶ)ったとのことにござりまする。となれば、諏訪頼重と村上の間でも同じような密約があったと考えられ、この三者は明らかに当家だけをないがしろにする動きをし、われらが血を流して手にした佐久や小県を喰いものにしたのではありませぬか」
原虎胤は怒りを露わにした。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。