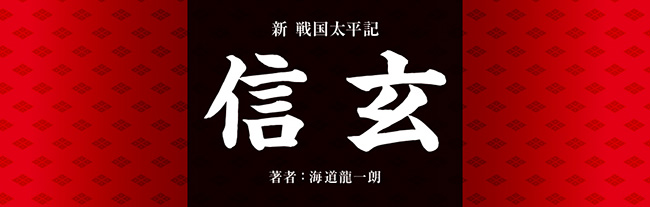第三章 出師挫折(すいしざせつ)18
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
この翌日から、晴信は悲しみを吹っ切ろうとするが如(ごと)く仕事に邁進した。
新たに加わった禰津(ねづ)元直(もとなお)と一族の協力もあり、まずは佐久(さく)の仕置に取りかかる。
同時に、今川(いまがわ)家から仕官してきた山本(やまもと)菅助(かんすけ)が加わり、竜王鼻(りゅうおうばな)の治水も進み始めた。
人、来たりて、人、去る。
己が好む、好まざるに拘(かかわ)らず、縁は巡り続ける。それが良い縁であろうと、悪しき縁であろうと。
――戦国の乱世ならば、なおさらのことだ。ただ、時と共に縁は巡り、人来たりて、人去る。されど、去る人よりも、来る人が少なければ、国は衰退していく。もしも、国を栄えさせたいと考えるならば、人材や民を寳(たから)として増やしていくしかない。
晴信はそんなことを痛感しながら、前に進もうとしていた。
まずは佐久から小笠原(おがさわら)家の影響を排除するため、長窪(ながくぼ)城の大井(おおい)貞隆(さだたか)の討伐を決める。
その直前に禰津元直が、大井の家臣、想木(あいき)昌朝(まさとも)と芦田(あしだ)信守(のぶもり)を調略し、武田家に内応するという約束を取りつけていた。
晴信は佐久の前山(まえやま)城を陣とし、長窪城へ攻め寄せる。想木昌朝と芦田信守の内応もあり、この城は呆気なく落ち、大井貞隆を捕縛した。
その余勢を駆り、岩尾(いわお)城と望月(もちづき)城も攻略する。これにより、武田家は佐久のほぼ全域を奪還して年越しを迎えた。
その翌年、捕縛されていた藤澤(ふじさわ)頼親(よりちか)が逃亡し、再び叛旗(はんき)を翻す。これに呼応し、高遠(たかとお)頼継(よりつぐ)も再び諏訪に兵を向け、武田家と相対することになった。
晴信は上伊那(かみいな)の制覇を目指し、天文十四年(一五四五)から高遠と藤澤の連合軍と激しい戦いとなる。高遠一揆(いっき)の中でも主力だった保科(ほしな)正俊(まさとし)を寝返らせ、ついに高遠頼継を高遠城から敗走させた。
高遠頼継は藤澤頼親の籠もる福与(ふくよ)城へ逃げ込むが、武田勢はここを包囲して激しい攻防を繰り返す。そして、落城寸前にまで追い込んだ時、新たな敵が出現した。
それが信濃(しなの)守護、小笠原長時(ながとき)の軍勢である。
長時の実弟、小笠原信定(のぶさだ)が南の鈴岡(すずおか)から援軍として現れ、天竜川(てんりゅうがわ)対岸の竜ケ崎(りゅうがさき)城に着陣した。
これに対し、晴信は信方と今井(いまい)信甫(のぶすけ)の二隊を荒神山(こうじんやま)に向かわせ、小笠原勢の侵攻に備えた。上伊那の軍勢と小笠原勢の合流を阻止するためである。
次々に現れる敵に、息つく暇もないどの戦いが続く。
しかし、その中で、いくつか朗報もあった。
武蔵(むさし)で扇谷(おうぎがやつ)と山内(やまのうち)の両上杉(うえすぎ)家と熾烈な戦いを繰り広げていた北条(ほうじょう)氏康(うじやす)から、晴信に関係改善の打診があったのである。
それを受け、武田家から駒井(こまい)昌頼(まさより)と向山(むこうやま)又七郎(またしちろう)が会談に赴き、北条家々臣の桑原(くわばら)盛正(もりまさ)と盟約の取り交わしについて話し合った。
北条家は河東(かとう)の地を巡り、今川家とも対峙(たいじ)していたため、武田家と盟約を結べないかと申し入れしてきたのである。
上伊那で戦っていた武田にとっても、悪い話ではなかった。佐久の支配も含め、北条家が同盟を望むならば、渡りに舟の申し入れだった。
北条家との関係改善が前向きに進む中、晴信は福与城へ総攻撃をかけ、ついに高遠頼継と藤澤頼親を降伏させる。これにより小笠原信定の軍勢は何もできずに撤退するしかなくなった。
晴信は巧みな手腕で難局を乗り切り、ついに上伊那までを掌中に収めた。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。