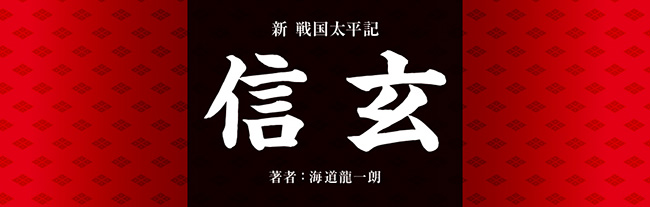第五章 宿敵邂逅(しゅくてきかいこう)10
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
「では、御今上への拝謁が終わりました後に、改めて歌会の日時などお知らせさせていただきまする」
近衛稙家は当然のことながら、景虎が歌道に傾倒していることを知っていた。
「さような歌会ならば、余も参加せねばなるまい」
足利義輝が口を挟む。
「よしなに」
笑みを浮かべた近衛稙家が答える。
「弾正、こたびの逗留(とうりゅう)は長くなりそうだな」
そう言い、義輝は嬉しそうに笑った。
景虎が征夷大将軍への拝謁と歓待の儀を無事に終えた翌日、朝廷から武家伝奏役の広橋国光が訪ねてきた。
武家伝奏役は、暦が変わる皐月朔日に土御門東洞院の里内裏で御今上への拝謁が許されたことを伝える。
景虎は謹んでこれを受け、返礼として御今上と朝廷への寄進を申し出た。
予定通り、御今上に拝謁し、景虎は上洛の褒美として「五虎退吉光(ごこたいよしみつ)」の銘刀を拝領する。
五虎退は通称であり、鎌倉時代の名刀工、粟田口吉光に鍛えられた腰刀だった。
その刃文を見て、五匹の虎が逃げ去ったという逸話を持ち、第三代征夷大将軍の足利義満(よしみつ)から朝廷に献上されたものである。
拝謁の儀の後、朝廷の関白と三公(左大臣、右大臣、内大臣)が揃(そろ)った席で「従四位下、左近衛権少将」の叙任が言い渡された。
この時初めて、景虎は関白の近衛前嗣と対面する。
――思うていたよりも、ずいぶんとお若い。
それが正直な感想だった。
近衛前嗣は足利義輝と同じ齢二十四である。
上洛の目的であった公方と御今上への拝謁を無事に終え、景虎は大いに面目を立てた。
幕府からは「文の裏書」、「塗輿(ぬりごし)」、「菊桐(きくきり)の紋」、「朱柄(あかえ)の傘」、「屋形号」を使用する許可が下され、すでに父の長尾為景(ためかげ)が許可を得ていた「毛氈(もうせん)の鞍覆(くらおおい)」、「白傘袋」の使用と併せ、七つの御免許となる。
これら上洛の褒美は、三管領(かんれい)家への待遇にも匹敵するほど破格の待遇だった。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。