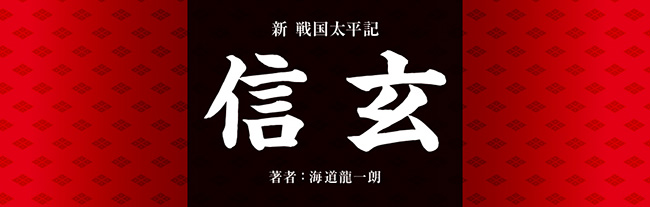第六章 龍虎相搏(りゅうこそうはく)2
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
「されど、駿河守殿。御屋形様は何よりも大義を重んじる君主ではありませぬか」
「大義も大事だが、赤の他人のために間尺に合わぬ戦を強いられる家臣は鬱憤が溜まるだけではないのか。前(さき)の出兵も然(しか)り。御屋形様が幕府から賜った大義の御旗を押し立て、坂東での筋目を正すための戦い、しかも坂東の諸侯に望まれ、総勢十万余にも及ぶ軍勢の総大将を務められ、確かに他人には義将の面目躍如たる合戦と見えておるやもしれぬ。されど、われらの如き身内の中には、さように思わぬ者も多いのではあるまいか。御屋形様は人が好すぎる。だから、京の公方や関東管領に誑(たぶら)かされるのだ」
いつになく辛辣(しんらつ)な定満の言葉に、柿崎景家が驚く。
「確かに、あの戦には、それがしも思うところはありまする」
「景家、遠慮なく本音を申せ。二人だけの話なのだ」
「……わかりました。それがしには御屋形様ではなく、あの戦に参じた者どもが歪(いびつ)に思えまする。その証左に、御屋形様への帰順を誓って総大将の采配を渡したはずの者どもが、いざ小田原城総攻めの御下知があると、一様に臆して兵粮攻めなどを具申し始める。それを怯懦(きょうだ)と言わずに、何と申せばよいのか! 御屋形様の軍略には、さような差出口(さしいでぐち)など無用。下知された策通りに戦い、下知された策通りに勝てばよかったのだ!」
景家は憤慨した口調で本音を吐露する。
「確かに小田原城攻めでは、思うようにならぬこともあり、北条に止(とど)めを刺すことができなかった。されど、十万にも及ぶ寄り合い所帯の軍勢であらば、号令一下といかぬことも出てこよう。あれはあれで、一戦の姿ではないか」
宇佐美定満はなだめるような口調で言った。
それでも景家はわずかに紅潮した顔で腕組みをする。前の関東侵攻について、どうしても得心がいかないことがあるようだ。
「駿河守殿、あの合戦こそがいかに間尺に合わぬものであったかは、終わった後の成田長泰の一件を見れば明らかにござりましょう」
その事件とは、景虎が行った無礼打のことだった。
「確かに御主が申す通り、あれは御屋形様にとっても、われらにとっても侮辱以外の何物でもなかった。あの時のことは、いまでもこの脳裡に焼き付いておるよ」
小田原城の包囲を解いた後、閏三月十六日の午後、景虎が山内上杉の名跡を嗣ぎ、上杉政虎として関東管領職を襲名する儀式が行われた。
坂東勢は新たな関東管領職を迎えるため、臣下の礼をもって鶴岡八幡宮の参道に整列した。
坂東の諸将が一様に下馬し、上杉政虎を待つ中、ただ一人の武将だけが馬に跨(またが)ったまま参列していたのである。
それが武蔵忍城の城主の成田長泰であった。
その姿を眼に留めた政虎の表情が急変する。
普段は至極冷静な主君の顔がみるみるうちに紅潮していく様を、宇佐見定満ははっきりと覚えている。
この長老が止める間もなく、政虎は愛駒を寄せ、無言のうちに扇で成田長泰の烏帽子(えぼし)を打ち払う。
『……な、何をなさりまするか』
成田長泰が驚愕(きょうがく)しながら政虎を睨みつけた。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。