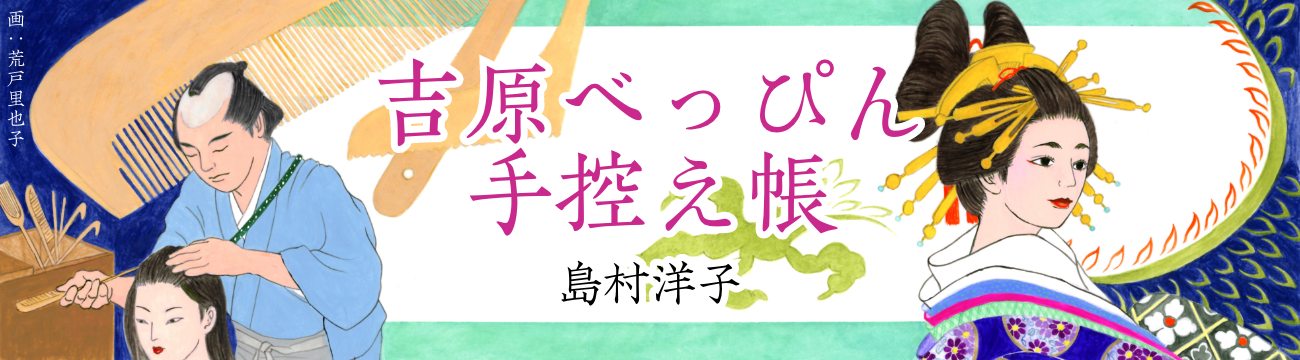第二話 おばけ騒ぎ始終
島村洋子Yoko Shimamura
親類の葬式に母親が出掛けていることを知っている男をお峰はすぐに信用した。
「おっかさんはどんな具合ですか」
とにかく母親のことが心配だった。
「とにかくすぐにお峰ちゃんに知らせなくてはってことで頼まれて、あっしもよくわからねぇんですが、叔母(おば)の娘のお初(はつ)さんからの言伝(ことづ)てで」
お初の名前が出て、ますますお峰はその男を信用した。
ただ男の口から出てくる言葉が佐倉のほうの強い訛りではなく、ちゃきちゃきの江戸っ子といった風なのがちょっと気にかかったが。
「おとっつぁんが帰ってきてからの相談でいいでしょうか」
とりあえず弟ひとりを残していくのも心配なので父親にひととおり話して判断を仰ぎたかった。
男はうっと一瞬黙ったが、
「いや、そんな余裕はねぇですよ。とにかくもうこのまま行かないと」
とお峰を急がせた。
まだ弟も小さいので、いま母に何かあったら困る。
もし少しでも動けるなら自分が連れて帰らないとと思いながらお峰はじゃあこれだけは、と弟の枕の下に書き置きを残した。
「よばれたのでおっかさんをむかへにいきます」
と書いておいた。
のちにこれがあったことによってお峰がただの家出ではないとわかったのである。
お峰は着の身着のまま、よく知らない男の提灯(ちょうちん)を頼りに夜道をついて行った。
幸い月は大きく光っていたのでなんとなくだが、あたりの様子はわかった。
川沿いを歩いていたのだが右に行くはずが、どういうわけか左に歩いていく。
「佐倉はこっちに行ったほうが近いんでは?」
と言うお峰の言葉に落ち着いた口調で男は言った。
「いえ、こっちに迎えの駕籠(かご)を用意してますから」
「駕籠?」
お峰はそんな贅沢(ぜいたく)な物に生まれて一度も乗ったことはない。
娘の足では到底無理だと思われているのだろうか。
母はそんなに急激に悪くなったのだろうか。
もしそうなら父と弟も連れてきて一目会わせてやるのだった。
そう思うと涙が出そうになる。
しかし男は足を休めもしない。
とにかく無言で月明かりの中をどんどん進んでいく。
お峰は誰もいない真っ暗な大海をこの男を頼りに泳いでいるような気持ちになっていた。
「駕籠はどこらにあるんでしょうか」
とお峰が言った時、男は振り向いた。
その振り返った恐ろしい顔を、お峰は時々思い出していまでもすくみあがることがある。
「そんなもん、ありゃしねぇよ」
男はそう言ってお峰のみぞおちを思いっきり殴ってきた。
お峰の記憶があるのはここまでである。
そのあとは目が覚めたら掘っ立て小屋よりは少しましなぼろ家に何日かいた。
世話をする老婆と、そして見張りの男がいた。
見張りは何人かが交代だったがいままでろくな仕事をしてきていないのは見た瞬間にわかるような手合いだった。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。