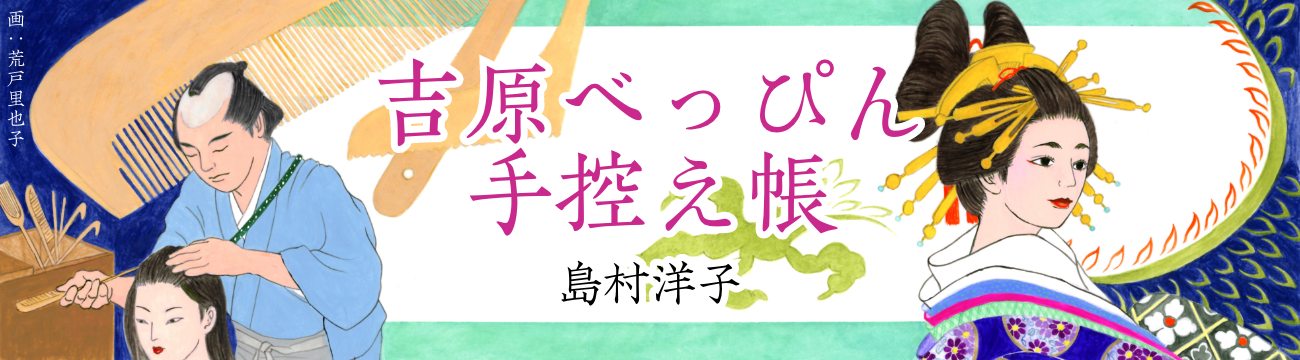第一話 金泥の櫛(くし)
島村洋子Yoko Shimamura
十八
龍田川は土左衛門が持っていた櫛について考えていた。
自分の持っていた櫛がもしそれならどうしようと怯えきっているお美弥もかわいそうだし、あんなまがい物を渡されても迷惑だと半ば怒っているような態度の梅香のことも気になっている。
吉原で起こる他人のことには関(かか)わらないのがうまく生きていく方便なのはよくわかっていたが、花魁という皆の上に立つ者として下の者もなんとか気持ち良く生きてほしいという思いが龍田川にはあった。
この吉原を出て新しい生活が待っているとは夢にも思えなかったし、行き倒れの母が赤子の自分を連れていたという話しか知らない天涯孤独な身であるのにもかかわらず、毎日豪奢(ごうしゃ)な生活ができている。
禿の時から人間の裏表を見過ぎて、男も女も信用できないのはわかっている。
男は結局、こちらに言うことをきかせたいだけだし、女は何をやっても嫉妬の材料にする。
こちらはどんなに位が高いと言っても所詮は買われる身、そんな普通の人間みたいな望みを持つこと自体が甘いのかもしれない。
ただ最近は、出入りの髪結い、亀屋の清吉だけは信じていいような気がしていた。
感覚が合うというのか話をしていてもこちらのことを先回りして理解するようなところがあって疲れない。
髪を結う頻度も心なしか増えてきている。
そんな頃、清吉が龍田川の髪をとかしながら言った。
「だいたいわかりました。といってもほとんどあっしの考えたことなんですが」
清吉はそう言って語り出した。
「あの櫛と笄は塗安という名のある漆職人の仕事でして、それをもとにまがい物がいくつか作られたのだとわかりました。作ったのはたぶん塗安本人です。話は同業者にも伝わっていないんで食いかねたうえでの仕業だと思います。いろいろ不幸が重なり本人はやる気を無くして呑んだくれの様子です。そこにどういういきさつか知りませんが、それに気がついたかつての弟子が娘ふたりが吉原に売られたと聞いて、娘に会いに来たんでしょう」
龍田川は思わず声をあげた。
「ふたり? ということはもしかして」
「そうです、娘のひとりは梅香です。梅香は塗安の娘のお梅です」
そうなると梅香は自分の父の作ったものをまがい物と見抜き、気に入らなくて使わなかったということになる。
梅香がそれほどの目利きになったのは父の一流の仕事を見て育ったからなのに、今度はその目によって父の仕事を否定したことになる。
なんという因果だろう。
龍田川は唾を呑(の)み込んだ。
「そしてここもよくはわかりませんけど、どういうわけかお美弥の客としてその弟子は十日にあけず通ってくることになります」
鏡越しに見える清吉の手の動きは相変わらず鮮やかである。
「お美弥に惚れて通っていたのかお美弥の頭に挿しているものが欲しくて通ったのかはわかりませんが、お美弥の櫛を盗むことはできたんでしょうね。師匠の恥となるものをいつまでも野放しにはできないと思ったのかもしれません」
「梅香とは名乗りをあげて話せたんだろか」
もしそうならこの前、金平糖を食べながら話した時に隠さず言いそうなものだけれど。
「いやそれが全く知らないらしいと言ってるんでさあ。見たこともない人で、たまになにかの時に櫛やら帯やらの話はする客もあるけれどそこで親の話でもされたら忘れるわけはない、と」
そう言っているうちに髪は見事に仕上がっていた。
「でも梅香の小間物入れから櫛を盗んでいったのは塗安の弟子の吉蔵に間違いないと思いますよ」
「どうやって客の男が自分の贔屓でもない女郎の小間物入れにたどり着くんだろう」
龍田川には不思議でならなかった。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。