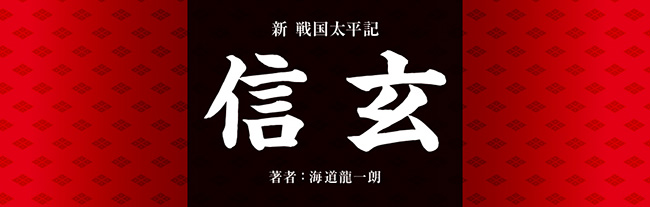第三章 出師挫折(すいしざせつ)4
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
『ゆえに兵は詐(さ)をもって立ち、利をもって動き、分合(ぶんごう)をもって変をなすものなり。ゆえに、その疾きこと風のごとく、その徐(しず)かなること林のごとく、侵掠(しんりゃく)すること火のごとく、動かざること山のごとく、知り難きこと陰(いん)のごとく、動くこと雷震のごとし。郷を掠(かす)むるには衆を分かち、地を廓(ひろ)むるには利を分かち、権を懸けて動く。迂直(うちょく)の計を先知する者は勝つ。これ軍争の法なり』
兵法第七、軍争篇の第三節の言葉である。
『兵は相手を詐(いつわ)る計略をもって立ち、自らの有利を求めて動き、分散と集合を繰り返して変化するものなのである。ゆえに、その疾さは風のように、その徐かさは林のように、侵掠する時は火のように、動かない時は山のように、存在を陰のように隠し、動く時は雷震が走るように素早く。隙を狙って郷を奪うには衆を敵味方に分け、領土を広げる時には味方へ利を分け与え、覇権をかけて動く。迂直の計、すなわち曲がりくねった道を真っ直ぐな道に変えるような計略を先に知っている者だけが勝つ。これが軍争の原則である』
そんな意味だった。
孫子の記した兵法は、第一の計篇から第十三の用間篇に分かれているが、第七の軍争篇は実際に戦場でどのように軍勢を動かすべきか、いわば実践について綴(つづ)られている。
晴信が思い出したのは、用兵の妙が記された箇所だった。
「……いかがなされました、晴信様」
原昌俊が急に黙り込んだ晴信を案じるように言う。
「……済まぬ。孫子の一節が思い浮かんで頭から離れなくなってしまった」
「ああ、なるほど。軍争篇にござりまするか」
微(かす)かな笑みを浮かべ、原昌俊が頷く。
「まさに、あれらの説が役立ちそうな局面」
この漢(おとこ)も孫子の全篇を暗誦(あんしょう)できるほど幼い頃から学んでいた。
いや。孫子だけではない。この書に始まり、三略(さんりゃく)、六韜(りくとう)、呉子(ごし)、尉繚子(うつりょうし)、司馬法(しばほう)、李衛公問対(りえいこうもんたい)に至る武経七書(ぶけいしちしょ)のすべてである。
原昌俊だけでなく、他の重臣たちも物心ついた頃から武経七書を学んでいた。
武経七書は宋(そう)の時代に武官を養成するための必読書として選ばれて以来、日の本においても武人の経典として扱われている。
晴信はまだ七書のすべてを会得したばかりだが、特に孫子への思い入れが強かった。
「加賀守、そなたもさように思うか」
「ええ、思いまする」
「ならば、こたびは一気に攻め入り、相手を追い落とす疾さが、迂直の計となるということか」
「はい。敵がこちらの力を量ろうと待つのならば、量る前に素早く押し切ってしまう。つまり、疾さを力に変える計略が有効と考えまする」
「知り難きこと陰のごとく、動くこと雷震のごとし。伏兵を使った一気の攻め、こたびの計略の要諦は、疾さを力に変えるということか」
晴信は得心したように呟く。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。