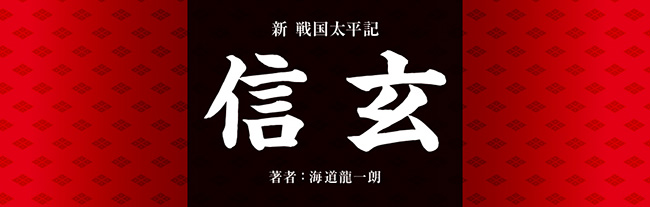第五章 宿敵邂逅(しゅくてきかいこう)4
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
そして、平柴の大黒砦からは、さらに険しく細い追手道(おうてみち)があり、やっと城門へ辿(たど)りつける。そこに数台の小荷駄車が入っていく。
「栗田(くりた)殿、いよいよ最後の鉄炮(てっぽう)百丁が届きましたな。これで計三百丁。明日にでも、この城に武田菱(びし)の旗幟(きし)を掲げられますぞ」
山本(やまもと)菅助(かんすけ)が小荷駄を見ながら、善光寺別当職の栗田寛久(かんきゅう)を励ますように言う。
「ええ、心強い限りにござりまする」
越後(えちご)から寝返った栗田寛久を籠城させるため、晴信は三千の兵を援軍として送り、防御を高めるための改修を菅助に命じていた。
そして、敵の城攻めを困難にするため、三百丁の鉄炮を揃えた。武田勢の戦で初めて使われる得物(えもの)である。
「この城を狙い、坂を登ってくる越後勢は、すべて撃退いたしまする。麓から城へ寄せるためには、菅助殿が造った地獄坂の一本道しかありませぬゆえ」
香坂(こうさか)昌信(まさのぶ)は鉄炮を構える仕草をする。
この守将が言ったように、今回の改修の要諦は、まさにその点にあった。
里から城を目指して登攀してくる敵は、高所から丸見えである。そして、最初の難関、大黒砦が待ちかまえている。入口には馬防柵(ばぼうさく)が立てられて騎馬の侵入を防ぎ、足軽が近づこうとしても、複雑な形に並べられた逆茂木(さかもぎ)が著しく動きを制限するようになっていた。
これにまごつく敵の寄手(よせて)を、まずは大黒砦から鉄炮と弓箭(きゅうせん)の攻撃で撃退しようという構えになっている。もしも、敵方が犠牲を顧みずに大勢で力攻めを行い、砦を突破したとしても、城へは急坂の細い一本道しかない。
せいぜい足軽が二列になって登るぐらいの幅しかなく、城からはその姿が丸見えとなる。つまり、鉄炮や弓箭の格好の的となるはずだった。
城方は追手門と城壁に造られた狭間(さま/射出口)から、一斉に鉄炮の攻撃を浴びせかけることができる。まさに下から這い上がる者にとっては地獄、上から鉄炮を撃つ者たちだけが極楽。
それゆえ、城兵たちは、この一本道を地獄坂、城の入口を極楽門と名付けていた。
「それがしは武田家に身を預けて、まことに良かったと思うておりまする。皆様方の手際良さには、目から鱗(うろこ)が落ちました」
栗田寛久が小刻みに頷きながら呟(つぶや)く。
「疾(はや)きこと風の如(ごと)し。動くこと雷霆(らいてい)の如し。御屋形(おやかた)様は緩慢な働きを最も嫌われるゆえ、武田の者は動き始めると立ち止まることを忘れてしまいまする」
香坂昌信は苦笑をまじえて言った。
「鉄炮をすぐに修得なされた香坂殿、そして、菅助殿の築城術には、ほとほと感心させられました。越後では家臣が皆、長尾(ながお)景虎(かげとら)の顔色を窺(うかが)い、命が下るのを待っているだけ。それに較べ、武田の方々はそれぞれが一芸に秀でており、自由闊達(かったつ)に動かれている」
寛久の世辞に、武田家臣の二人が顔を見合わせる。
「いやいや、それを許してくださる御屋形様の器量があればこそ、の結果にござる。それに、まあ、それがしは城の表裏を少しばかりいじっただけのこと」
山本菅助は城の裏側にも忍び返しを仕掛けていた。
正攻法が無理ならば、越後の忍び、軒猿(けんえん)による陽動があるかもしれないと予測していたからである。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。