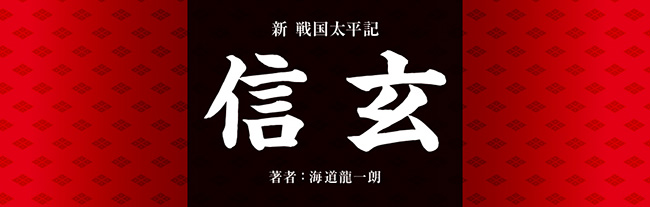第六章 龍虎相搏(りゅうこそうはく)3
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
『先に戦地にいて敵軍の到着を待ち受ける軍勢は楽だが、後から敵の待つ戦地に着き、休む間もなく戦いにおもむく軍勢は疲弊してしまう。
ゆえに巧みに戦う者は、敵を思うがままに動かし、決して敵の思うままに動かされたりはしない。
敵が来てほしい処に、敵自らがやって来るように仕向けられるのは、利になるように見せかけて誘うからである。敵が来てほしくない処に、敵自らが赴かないようにさせるためには、害になるように見せかけて引き留めるからである。
ゆえに、敵がゆるんでいれば、これを疲労させ、飽きるほど食べていれば、これを飢えさせ、安らいでいれば、これを誘って動かせばよい』
まさにここで語られていることは、川中島へ先に布陣した越後勢と己の関係を明示していた。
――それゆえ、急にこの一節が思い浮かんだのであろう。まさにここで語られているが如く、川中島へ先に布陣した越後勢は、充分に態勢を整えながら、われら武田勢を待てばよい。一見、無謀に見える景虎の布陣も、しっかりと虚実の煙幕を張り、思い通りにわれらを動かそうとしている策謀なのかもしれぬ。そこには、こちらの布陣さえも制限しようという魂胆が見え隠れしている。ならば、最も利のありそうな場所に布陣することこそが、最も下策になるということかもしれぬ……。
すでに戦いの駆け引きは始まっていた。
――おそらく、総軍で行う評定では、最初に布陣する場所について紛糾するであろう。されど、その場所こそが最も重要となる。後々の戦いと、勝敗の行方さえ左右すると言っても過言ではなかろう。
いったん脳裡で思案が巡り出すと止まらなくなるのが、この漢の特性だった。
信玄はさらに思案を練るため愛駒の鞍(くら)から下り、塗輿(ぬりごし)に乗り換える。棒道を進む間、じっくりと思案に耽(ふけ)ろうと考えたからである。
棒道を抜けた武田勢は、小渕沢(こぶちざわ)の笹尾(ささお)砦に向かう。ここで初日の宿営をするためだった。
城に入ってからも、信玄の思案は続く。
先ほどの一節に続けて、さらに孫子は説いている。
「二、
其(そ)の必ず趨(おもむ)く所に出(い)で、其の意(おも)わざる所に趨(おもむ)き、千里を行(ゆ)いて労(つか)れざるは、無人(むじん)の地を行けばなり。
攻(せ)めて必ず取るは、其の守らざる所を攻むればなり。
守りて必ず固(かた)きは、其の攻めざる所を守ればなり。
故(ゆえ)に善(よ)く攻むる者には、敵、其の守る所を知らず。
善く守る者には、敵、其の攻むる所を知らず。
微(び)なるかな、微なるかな、無形(むけい)に至る。
神(しん)なるかな、神なるかな、無声(むせい)に至る。
故(ゆえ)に能(よ)く敵の司命(しめい)を為(な)す」
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。