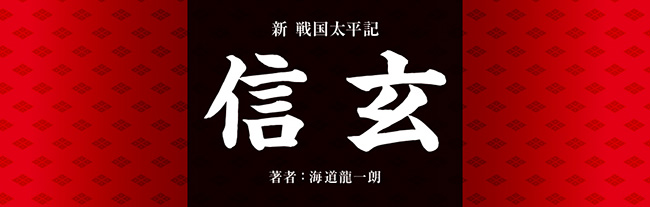第三章 出師挫折(すいしざせつ)5
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
「しかも、今回の手際だ。まさか、これほど呆気(あっけ)なく小笠原を打ち破るとは考えてもみなかった。確か、まだ齢(よわい)二十過ぎと聞いたが、ここまでやってくれるとはの。やはり、只者(ただもの)ではないと見るべきであろうな」
「信濃守殿、武田晴信が初陣の時に殿軍(しんがり)を預かり、退却すると見せかけながら平賀(ひらが)源心(げんしん)の海ノ口(うんのくち)城を奇襲で抜いたという話を聞いたことがありませぬか?」
「ああ、確かに、さような風聞を耳にしたことがある」
「その時の傅役(もりやく)は板垣信方と申し、武田家中でも名うての武辺者(ぶへんもの)でありながら、先代の信虎には冷遇されていたようにござる。初陣の奇襲も、かの者が企てたと聞いており、板垣信方が若き晴信を押し上げ、操っているのではありませぬか。それに協力する重臣たちもおり、信虎の隠居は冷飯を喰わされていた武田の家臣が仕掛けた謀叛(むほん)だったのではありますまいか」
「晴信がただの御輿(みこし)に過ぎず、実際は有能な重臣たちがすべてを取り仕切っていると?」
「信虎の佞臣(ねいしん)であった者たちを除けば、主だった家臣はそのまま晴信の側に残っていることからも、揃って旧主から離反したのではありませぬか。元々、武田の家臣は能ある者が多いと聞きました。されど、暴君であった信虎に押さえ付けられ、爪を隠して従順な振りをするしかなかったとも」
「晴信の代に替わり、能ある鷹どもが誰に憚(はばか)ることもなく爪を出し、本領を発揮し始めたということか」
「そうとでも考えなければ、一連の出来事は辻褄(つじつま)が合いませぬ」
「ふぅむ……」
高遠頼継は眼を細め、腕組みをする。
「……武田晴信が只ならぬ器量の者なのか、あるいは優れた家臣たちが縦横無尽に動き始めたのか、はたまた、その両方なのか。いずれにしても、こたびのことで頼重は窮地に立たされた。ここはひとつ、勢いを取り戻した武田を使うてみるか」
「と、申されますると?」
小首を傾げながら、藤澤頼親が訊く。
「箕輪殿、われらの当面の敵は諏訪頼重ではないか」
「ええ、それは確かに。頼重に引導を渡し、信濃守殿に諏訪一門の惣領となっていただくのが、われらの望み」
「ならば、敵の敵は、味方も同然。そうとも考えられる」
「敵の敵は、味方?」
「もしも、こたびの一件で、武田が小笠原を導き入れた責任を頼重に問うならば、両家は手切も同然となるであろう。つまり、盟約を反故(ほご)にされた武田は、諏訪を攻めねばならぬ」
「されど、頼重には晴信の妹が嫁いでいるではありませぬか。いわば、人質も同然。何らかの話し合いで元の鞘(さや)に収まるのではありませぬか」
「そうとは限らぬ。いや、さようなことをしてしまえば、晴信の面目は失われ、せっかくの代替わりがぶち毀(こわ)しとなってしまうのではないか。考えてもみよ、こたびのことは信虎が惣領であったならば、絶対に起こらなかったはずだ。されど、晴信が惣領となった途端に、頼重は小笠原と手を組み、その軍勢を招き入れた。それは完全に武田を侮ったということを意味している。妹への情に流され、その侮辱を看過すれば、晴信は惣領としての器量を疑われるであろうし、有能な家臣たちならば、さような愚挙を許すはずもない。加えて、もうひとつ、頼重を見限る理由もある」
「武田晴信が頼重を見限る理由……それはいかなる?」
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。