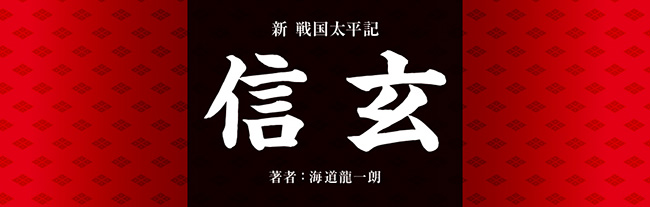第三章 出師挫折(すいしざせつ)5
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
「頼重に嫁いだのは確かに信虎の娘であるが、晴信とは腹違いではなかったか」
「あっ!?」
「信虎が隠居した後、多くの側室がどうなったかは知らぬ。されど、正室の子である晴信が側室たちとその縁者を厚遇しなければならない謂(い)われはなかろう。他家へ嫁いだ腹違いの妹も同様。非情と言われようとも、晴信は武田の惣領として盟約を破った頼重を糾弾せねばならぬ。それができぬならば、われらが手を組む価値もなかろう」
「なるほど」
「われらが少し武田を煽り、晴信が腰を上げたならば、一緒に頼重を討てばよい。幸いにも、武田への伝手(つて)ならば、身近にあるではないか」
「下社の堯存(たかのぶ)にござるか」
藤澤頼親が薄く笑う。
下社の堯存とは、諏訪大社、下社の大祝を自称する金刺(かなさし)堯存のことだった。
「さよう。かの者をけしかけ、武田が頼重を討伐するつもりならば、われらが協力するという話を持ちかけてみてはどうか。堯存ならば武田に知己の者がいるはず。なにせ、祖父の金刺昌春(まさはる)が甲斐で武田信虎の世話になっていたのだからな」
「それは妙案にござる。金刺昌春は諏訪頼満に攻められて下社を追われたゆえ、堯存も頼満の孫である頼重には恨み骨髄であろう」
「諏訪の血塗られた因縁は、元々、上社と下社の諍(いさか)いにある。そこに小笠原や村上(むらかみ)、武田が首を突っ込んだため、余計に怨恨が深くなったのだ。こうして、また役者が揃うたのならば、好機を逃さず、われらが両社を統一して諏訪の頂点に立つことを目指すべきではないか。それがしが一門の惣領となり、箕輪殿、そなたが両社の大祝宗家となればよい。そのためだけに、武田晴信を利用するつもりだ。傘下に入るつもりなど、毛頭ない」
高遠頼継が言ったように、諏訪の内訌はそのまま諏訪大社の権勢を巡る諍いであった。
諏訪大社と一口で言っても、それは諏訪湖を挟んで二社四宮からなり、南畔の上社には本宮(ほんみや)と前宮(まえみや)、北畔の下社には秋宮(あきみや)と春宮(はるみや)がある。
上社、下社と呼ばれて区別はされているが、両社に上下の順列はなく、上社の大祝は諏訪惣領家、下社の大祝は金刺家が嗣(つ)いできた。
『関より東の軍神(いくさがみ)、鹿島(かしま)、香取(かとり)、諏訪の宮』
そのように謳(うた)われた両社の大祝は、鎌倉時代から神人(しんじん)の一族を組織し、諏訪神党と呼ばれる有力な一揆(いっき)を育て上げ、余所者(よそもの)の侵入を許さなかった。
ところが当世になり、この両社の結束を揺るがす事件が起きる。
応永(おうえい)七年(一四〇〇)の大塔(おおとう)合戦と呼ばれる争乱で、信濃守護の小笠原家に対し、村上家を中心とする北信濃の国人衆が反旗を翻したのである。
この合戦に際し、上社の諏訪惣領家は北信濃の国人衆に与力して陣代を送るが、下社の金刺家はなぜか守護の小笠原家に味方することを選んだ。
これを契機として、上社と下社の対立が始まってしまう。
大塔合戦の後、信濃守護の小笠原長秀(ながひで)は、自分を裏切った諏訪の上社を目の敵にし、下社の後盾となって抗争を煽り立てた。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。