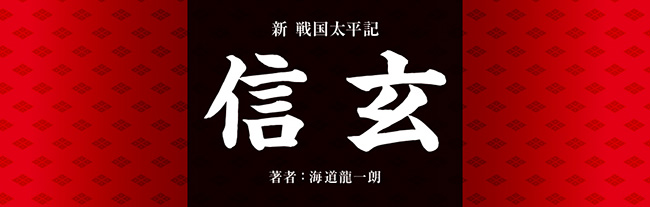第五章 宿敵邂逅(しゅくてきかいこう)2
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
二人は北曲輪の寝所へ入り、大井の方に太郎の具足姿を披露した。
「……立派になりましたね、太郎」
大井の方は半身だけを起こし、眼を潤ませる。
「花嫁御寮を迎えることも楽しみにしておりますよ」
「御祖母様、どうかそれまで、お軆(からだ)を大事に」
太郎も泪(なみだ)を堪(こら)えながら言った。
これが天文二十一年(一五五二)一月八日のことだった。
しかし、武田家に喜ばしいことばかりが続いたわけではない。
一月二十三日に、重臣の小山田(おやまだ)信有(のぶあり)が他界してしまう。
郡内(ぐんない)衆を率いる信有は、砥石崩れの一戦で負傷しており、この時の金瘡(きんそう)がもとで亡くなった。
そして、もう一人。ほとんどの者に知られず、この世を去った者がいる。
伊那(いな)郡高遠(たかとお)城の城主であった高遠頼継(よりつぐ)である。
武田家が上田原(うえだはら)で敗戦した直後、小笠原長時(ながとき)と共謀して諏訪西方(にしかた)衆が謀反を起こした。この影には高遠頼継もおり、もしも、小笠原が勝っていれば叛旗(はんき)を翻すつもりだった。
しかし、小笠原長時は敗走し、高遠頼継の内応は、腹心であった保科(ほしな)正俊(まとし)の注進により晴信に伝えられる。
この件に対する申し開きのために、高遠頼継は甲斐の府中へ出仕したが、その場で捕縛されて牢に幽閉された後、二十三日に自害させられた。
保科正俊は度重なる主(あるじ)の迷走に嫌気がさし、高遠家を見限り、武田家に仕えるために注進に及んでいた。
いつかは高遠頼継を仕置しなければならないと晴信も考えており、槍の名手と謳(うた)われた勇猛な武将が忠誠の証(あかし)を見せたため、ちょうど渡りに船の状況となったのである。
これを機に、保科正俊は伊那郡の押さえとして武田家に臣従することになった。
そして、暦が変わって如月(きさらぎ/二月)になると、晴信は駒井(こまい)政武(まさたけ)を駿府(すんぷ)に派遣する。今川義元の娘、嶺松院(れいしょういん)の輿入(こしい)れについて時期の詳細を決めるためだった。
二月六日に今川義元と面会した後、駒井政武が府中へ戻ってきた。
その一部始終を報告し、最も重要な題目について話し始める。
「御屋形(おやかた)様、治部大輔(じぶのたゆう)殿は婚儀の時期を『神楽月(かぐらづき)の頃が、よろしかろう』と仰せになられた後、和歌(うた)を一首、お読みになられました」
「いかような和歌であったか?」
「知らず来て、四方(よも)の宮居(みやい)の神楽月、立つ榊葉(さかきば)の音のさやけき。この一首を御屋形様にお伝えしてほしいと」
「なるほど、藤原(ふじわらの)定家(さだいえ)殿の歌か。風雅を尊ぶ義元殿らしい」
晴信が頷(うなず)く。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。