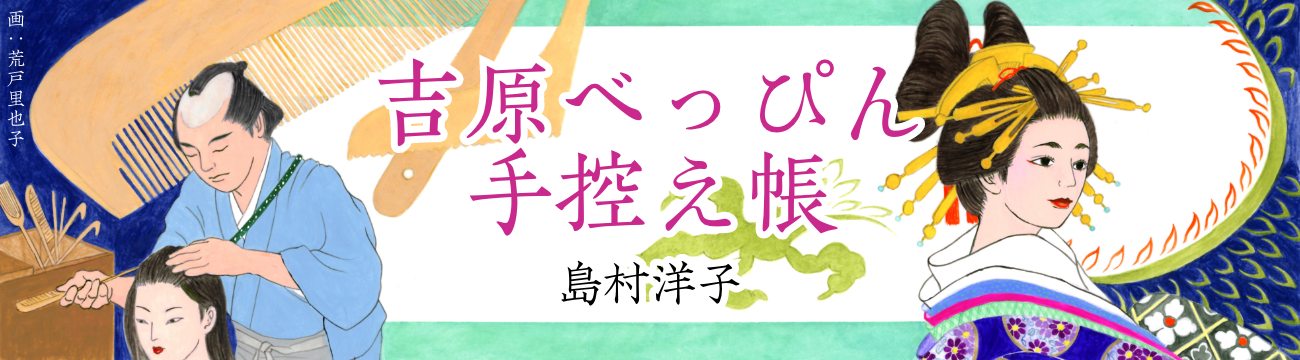第五話 夏ざかり宴競べ
島村洋子Yoko Shimamura
一
そろそろ大川(おおかわ)の花火ともなると江戸にも夏本番の活気があふれて来る。
この花火は八代将軍徳川吉宗(とくがわよしむね)の折にはやり病で死んだ庶民の追悼のため大川端で施餓鬼(せがき)法要をしたのが始まりで、例年の行事になった。
女郎(じょろう)たちは花火の上がるその頃がまさに稼ぎ時なのだが、ここ吉原(よしわら)でも角度によってはわずかに見える花火を楽しみにしている者たちもいた。
景気の良い旦那衆(だんなしゅう)は毎年その時刻に船を出して、花火見物という風流なことをすることもあった。
春日屋(かすがや)の大人気花魁(おいらん)龍田川(たつたがわ)に夢中の両替商小畑屋新五郎(おばたやしんごろう)もそのひとりである。
「花魁にも見せてやりてえなあ、真っ直(す)ぐ真上に上がるあの豪華な花火を、よう」
白髪交じりの四十男なのだが、どうしてその筋肉のある身体(からだ)はまだ青年のような精気にあふれている。
気に入った客だけに渡す本気の印のキセルをくれてやろうかと龍田川は考えないでもなかった。
半身を起こした新五郎の背中を見ながら龍田川は、小さく笑った。
「この世のうまいものを何でも食べられて、こうして誰も着られない羽二重(はぶたえ)で眠れても、外に出るのばっかりはあちきにはおよそかなわんことで」
そう言って龍田川は緋色(ひいろ)の襦袢(じゅばん)から手を伸ばして男の背に丸を書いた。
浮世絵で見たり人の噂(うわさ)に聞いても、龍田川自身は大川の花火を見たことがない。
花火に限らず、売られた者たちはこの吉原の外で起こることをほとんど見たことはないのだ。
しかし皆、つらいも悲しいももはや存在せず、自分の身の上はそういうものだと思っているから別段、残念でもない。
施餓鬼供養というのだから、自分が乳飲(ちの)み子のときに亡くなったという母の供養にもなるかもしれない花火を見たいものだと龍田川もそう思わないわけでもなかったが、どだい無理なものは無理な話である。
新五郎がしきりに残念がるのを見ているとかえって不思議な気持ちになるくらいだ。
龍田川の言葉を聞いて切なそうにしばらく黙っていた新五郎が突然、
「そうだ!」
と声をあげた。
「花魁、いいことを思いついたよ。ここで大きな花火を見せてやるよ」
龍田川はそれがどういう意味かよくはわからなかったが、
「へえ、そりゃ嬉(うれ)しゅうござんす」
ととりあえず礼を言うことにした。
この男にどんなに金があろうとそんなことは絶対に無理だろうと思いながら。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。