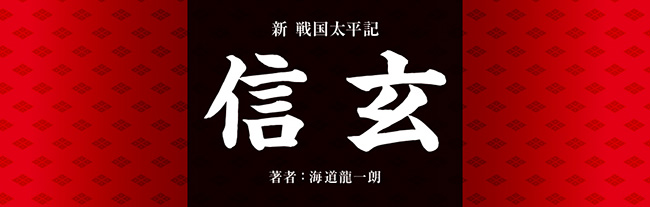第五章 宿敵邂逅(しゅくてきかいこう)6
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
『何もせぬとは……。さようなわけには、まいりますまい。城主ならば家臣に範を示さねばならぬのではありませぬか?』
『俄(にわか)城主の範など、誰が見習いたいと思うであろうか』
『えっ』
景虎が置かれた状況を、老師の「俄城主」という言葉が端的に顕(あらわ)していた。
『禅寺において新参の雲水(うんすい)が祖師の如き空口(からぐち)を叩いても、相手にされぬのと同じく、新参の城主が古参の家臣に物言うたとて、誰も耳を貸さぬ』
『……では、兄上から城主になれと言われたこの身は、いったい、どうすれば?』
『そなたは、馬に乗れるな』
『はい。……御師様に稽古を許していただいたので乗れるようになりました』
『兵法兵術も一通りは学んだか?』
『はい。……講話を施していただきましたゆえ』
『ならば、ただ馬に跨(また)がり、皆の待つ城へ入る。それで、よかろう。いや、それしかできぬな』
とりつく島もない言葉に、景虎は呆然(ぼうぜん)と師の顔を見つめる。
『ただ、馬に乗り、城へ入る……。それだけにござりまするか?』
『さよう。それしかできぬ分際なのだから、泰然自若として馬に乗り、慌てず騒がず、黙って城へ入ればよい。皆はまず、そなたの所作しか見ることができぬからの。俄城主でも、堂々とさえしておれば、何とか格好がつくであろう』
厳しい答えだった。
七年間も仏門にいた子息が急に還俗して城主になったところで、それは家臣たちが故あって担ぐ御輿(みこし)に過ぎない。従って、誰も統率力や指導力などを求めてはいないはずである。
反目する国人(こくじん)衆を押さえ込むには、それなりの大義や御旗(みはた)が必要であり、対抗する家臣たちはわかりやすい御輿を担いで力を結集しようとしているに過ぎなかった。
――それならば、余計な我を出そうとせずに、家臣たちが担ぎやすい御輿になればよい。
老師はそのように諭していた。
威光などというものは、担がれた後でついてくるもので、たかだか齢十四の若輩にそんなものを期待しているはずがないという見解(けんげ)だった。
しかし、景虎はそのように考えなかった。最初から威光を発するような城主の姿を、己に重ねようとしていたのである。
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。