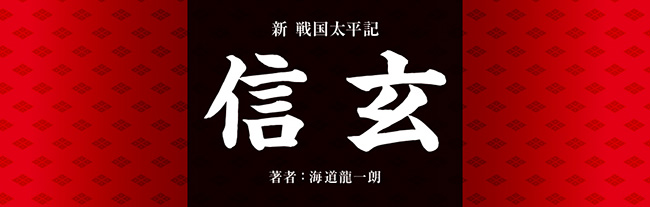第五章 宿敵邂逅(しゅくてきかいこう)6
海道龍一朗Ryuichiro Kaitou
東密とは空海(くうかい/弘法大師〈こうぼうだいし〉)が伝えた真言密教のことであり、真言宗の根本道場である教王護国寺を総本山とすることから、そのように呼称された。
空海は密教を大乗の最上位に置き、 大日如来(だいにちにょらい)を主尊とし、「金剛頂(こんごうちょう)経」よりは「大日経」を重んじた。
それに対し、天台(てんだい)宗が伝える密教は台密と呼ばれている。当初、天台宗は顕教であったが、最澄(さいちょう)、円仁(えんにん)、円珍(えんちん)らが入唐(にっとう)して比叡山延暦(ひえいざんえんりゃく)寺に密教を伝え、加持(かじ)祈禱を盛んにした。
そして、もうひとつが高野山(こうやさん)にある金剛峯寺(こんごうぶじ)であり、この寺院も真言宗の宗祖である空海が修禅の道場として開創しており、真言密教の聖地とされている。
金剛峯寺では南北朝の頃に「応永(おうえい)の大成(たいせい)」と称される古義派教学が大きく発展し、寳性院(ほうしょういん)の宥快(ゆうかい)が而二門(ににもん)の教学、無量壽院(むりょうじゅいん)の長覚(ちょうかく)が不二門(ふにもん)の教学を振興させ、古義真言宗を大成させた。
――いっそ、高野山へ登ってみるか。東密や台密にも惹(ひ)かれるが、京の近くよりも山深い金剛峯寺がよいかもしれぬ。とにかく、まずは畿内(きない)へ出ることが先決だ。
景虎は曹洞宗の寺院に掛錫(かしゃく)を願いながら、京まで行くつもりだった。
ある程度の路銀は携えてきたが、遊行も修養のひとつと考え、掛錫ができなければ野宿もかまわないと心に決めている。
すべての役目を放擲(ほうてき)してきたことに後ろめたさがないわけではなかったが、それよりも凡俗な重圧から解き放たれたような清々(すがすが)しさが勝(まさ)っていた。
修行していた頃の宗心(そうしん)という名に戻り、景虎は煩悩を振り払うように遊行の旅を続けた。
一方、景虎からの書状を見た師の天室光育は仰天する。
――家臣たちの内訌が起こったという話は聞いていたが、ここまで深刻であるとは知らなかった。とにかく、この件を家宰の直江殿に伝えねば……。
光育はすぐに春日山城の直江景綱の屋敷を訪ねる。
この禅師から事情を知らされた家宰も驚愕(きょうがく)した。主君が毘沙門堂に籠もっていると思いこんでいたからである。
「……ということは、すでに御屋形様は毘沙門堂にはおられぬと!?」
「おそらくは、その通りかと。昨日の払暁前に当寺開静番の雲水が書状を受け取っておりますゆえ」
「なんということであるか……」
直江景綱は呆然と呟(つぶや)く。
「これから毘沙門堂へ行って確かめましょう」
- プロフィール
-
海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう) 1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。