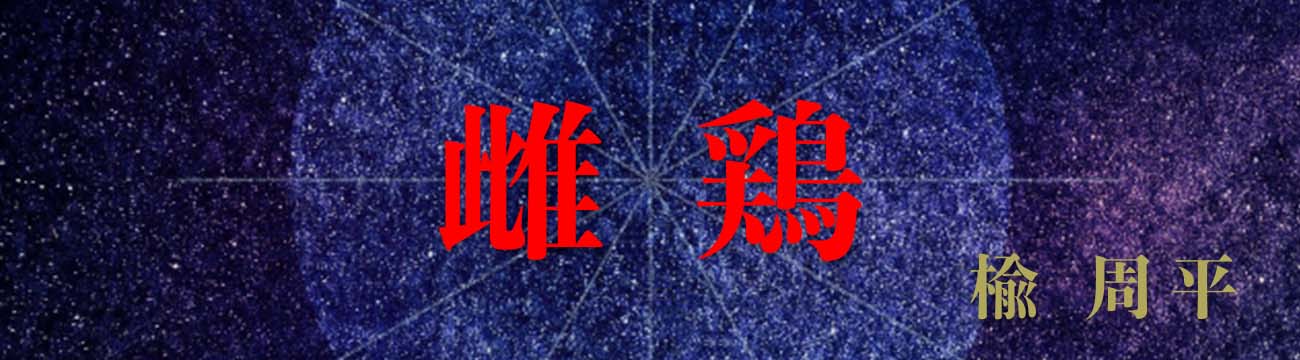第一章3
楡周平Shuhei Nire
貴美子は鬼頭の言葉が終わらぬうちに返した。「三が日でいつもより本数が少ないこともあってひと列車後になると、東京に戻るまでには二時間近くの違いが出てきます。それに、あの日、店で夕食を一緒に摂ることになっていたことは、私と清彦しか知りません。三が日最後の日の夕食なので、自宅で摂ることにしていたと。だから、清彦は千葉から真っ直(す)ぐ自宅に戻り、私の帰りを待つことになっていたと……」
「自宅は長屋だろ? 事件が起きた時刻に清彦が在宅していたかどうかを、警察は調べなかったのか?」
「調べたと思いますよ」
貴美子は即座に答えた。「でもね、先生。正月三が日の最後の日の夕食時ですよ。そんな時刻に外に出ている人は稀(まれ)じゃないですか」
「それはそうだが……」
それでも納得しない様子の鬼頭に向かって、貴美子は言った。
「それに私が刺青を入れに行く途中で、清彦は自宅に向かいましたの。千葉を発(た)つのが遅れたら、帰宅はちょうどその頃になったはず。隣の音が筒抜けなほど、壁が薄い長屋です。その辺りの時刻に人の気配があった。明かりがついているのを見たと証言する人がいたとしても不思議ではありませんでしょう?」
「つまり、アリバイをでっち上げることができたわけか」
納得した様子の鬼頭だったが、「で、その筋書きを考えたのは?」
すかさず問うてきた。
「私です」
貴美子が当然のごとく答えると、
「お前が? 人が二人も刺し殺される現場を間近で見た直後に、身代わり、刺青、アリバイと、よくも冷静でいられたもんだな」
目を丸くして驚きを露(あらわ)にする鬼頭だったが、その瞳が炯々(けいけい)と輝き出すのを、貴美子は見逃さなかった。
貴美子は気づかぬふりを装って、話を続けた。
「それに、弁護士の先生がおっしゃるように、やはりアメリカ側から、何らかの力が働いたとしか考えられないのです。警察も検察も、私の供述内容に疑問を持つ様子もありませんでしたし、清彦のアリバイについては調べたのかどうかもはっきりとは分かりません。とにかく、早く幕引きを図りたい様子が見え見えで……」
「アメリカ側か……」
鬼頭が何かを思いついたように、そう呟(つぶや)くと、続けて問うてきた。
「お前の処遇を巡って彼らの意向が働いた証拠、あるいは根拠になるものがあるのか?」
「先生、判決は懲役五年でしたが、実際には、私、四年半で出所しましたのよ」
「えっ……?」
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。