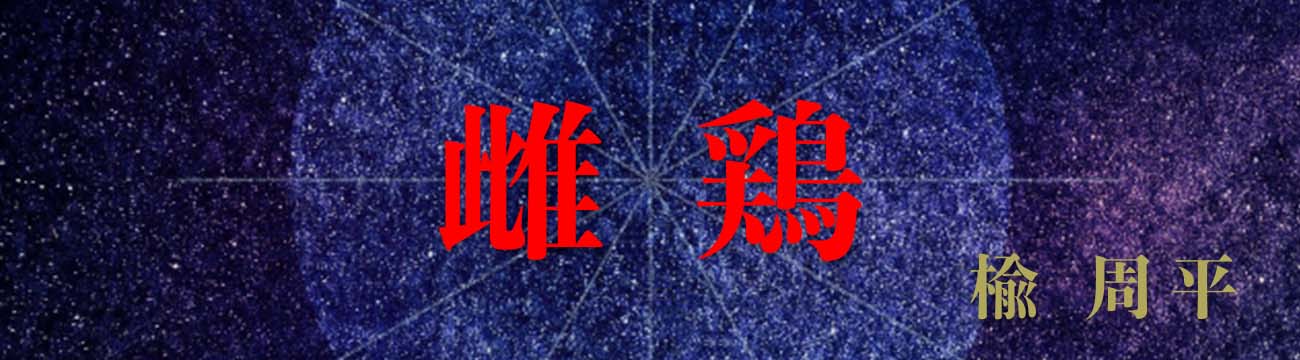第一章3
楡周平Shuhei Nire
再び胸の前で腕組みをし、口を噤(つぐ)んだ。
「大きな理由……ですか?」
「まあ、今ここであれこれ詮索しても仕方がない。それより、清彦との約束はどうなった? ニュー・サボイで働くようになったところを見ると捨てられたのか?」
鬼頭は話題を転じてきた。
「捨てられたと申しますか、拘置所にいる間に消息が途絶えてしまいまして……」
やはりと言うように、鬼頭は少し苦々しい表情を浮かべ沈黙する。
貴美子は続けた。
「面会が許されるとすぐに、拘置所を訪ねて来てくれましてね。私の身を案じてくれたのはもちろんですが、将来に希望を持たせなければという思いもあったのでしょう。『出所後は、自分たちのことを知る人がいない、遠く離れた土地で再出発を図ろう。その時に備えて、確固たる生活基盤を築くべく、即刻動き始める』と言い残したきり、ぱったりと音沙汰がなくなりまして……」
「すると面会に来たのは、その時だけか? たった一度しか来なかったのか?」
「手紙も沢山書いたのですが、三ヶ月も経った頃でしたでしょうか。弁護士の先生が、出した手紙を束にして持って参りまして、大家さんが家賃を滞納されて困っていると……」
「弁護士は先輩だと言ったが、彼にも行き先を告げずに行方をくらましたと?」
「ええ……」
その時覚えた不安は、決して忘れられるものではないが、清彦は縁もゆかりもない遠くの街で、自分を迎える日に備えて、必死に動き回っているのだろうと自らに言い聞かせることで、貴美子は心の安定を保とうとした。
しかしである。
「弁護士の先生も、内縁とはいえ、清彦の妻だから弁護を引き受けてくれたのです。清彦が消息を絶った、しかも私は殺人罪に問われるかもしれないのです。誰がどう考えたって、清彦が逃げたとしか思えませんわ。先生も判決が出てからは、刑務所を訪ねて来ることもなく、それっきり……。それでも、もしやと思って、刑期を終えたその日に、事務所に先生を訪ねてみたのですが、帝大の同期、同窓に訊ねても、誰も消息を知らないとおっしゃいまして……」
人間の本性、心の奥底に必ずや潜んでいる醜悪さが剥き出しになるのが戦場である。
鬼頭にしてみれば、さもありなんといったところか。それが証拠に内縁とはいえ、将来を共にすると誓い合った妻に殺人の罪を背負わせ、服役中に捨てた男を非難するでもなし、同情の言葉一つ口にするでもない。
「他も当たってみたのか?」
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。