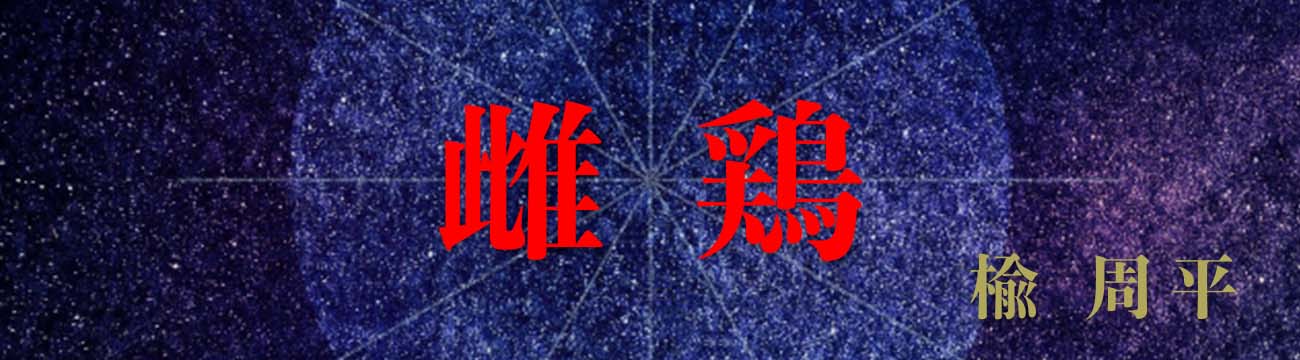第二章
楡周平Shuhei Nire
1
話には聞いていたが、秋の京都は想像を絶するほどに美しい。
空襲に一切遭わなかった京都は、戦前の街並みがそのまま残っている。
古都の名残を色濃く残す街に、紅葉した木々が混じり合う様は、まさに錦絵そのものだ。しかも朝昼夕と、陽の角度や光量によって、刻一刻と表情が変化していく。
鬼頭が鴨上に命じて用意させた家は、左京区の下鴨(しもがも)神社に程近い一軒家だった。
板塀に囲まれた敷地は六十坪ほどの広さがあり、庭に小さな池と、手入れの行き届いた庭木が植えられ、苔(こけ)に覆われた庭石が散在している。瓦葺(かわらぶ)きの住居は、昭和初期に建てられた三十坪ほどの二階建ての日本家屋で、その一階の一室が貴美子の仕事場となった。
京都に居を移して二週間、貴美子は自分の内心の変化に驚いていた。
面会が途絶えてからは、「私は捨てられたのではないか」と疑念に駆られる一方で、身代わりになった上に、生涯を共にすると誓い合った証として薬指に墨まで入れた女を捨てるはずがない。きっと清彦の身に、抜き差しならぬ何かが起きているのだと自らに言い聞かせることで、かろうじて心の安定を保ってきた。
しかし、さすがに音信がぱったり途絶えてしまうと淡い希望も失せてしまう。
前科者に向けられる世間の目がいかに厳しいものか、人間がどれほど簡単に心変わりするものか、同房者から散々聞かされたこともあった。だから出所後、清彦が消息不明となった現実を突きつけられても、「やはり」と思いこそすれ、それほど大きな衝撃は覚えなかった。
それでも清彦が、なぜ自分を捨てたのか。その理由は何であるのか。今、どこで何をしているのかを知りたい気持ちはどうしても捨て去ることができなかった。なぜなら、獄中で彼には絶対に告げなければならない重大事が起きていたからだ。
それが心機一転とはよく言ったもので、京都で暮らすようになってからは、吹っ切れたというか、一切気にならなくなったのだ。
「御免ください」
玄関から男の声が聞こえたのは、昼食の片付けを終えたちょうどその時だった。
声の主は分かっていた。
鬼頭の秘書を務める鴨上である。
応接間にいた貴美子は玄関に向かうと、引き戸を開けた。
「いかがですか、新居の住み心地は」
貴美子の姿を見るなり、笑みを湛(たた)えた鴨上が問うてきた。
「とてもいいお家です。東京で暮らしていた四畳半一間のボロアパートとは雲泥の差ですわ。これまで暮らしたどの家よりも、住み心地が良くて」
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。