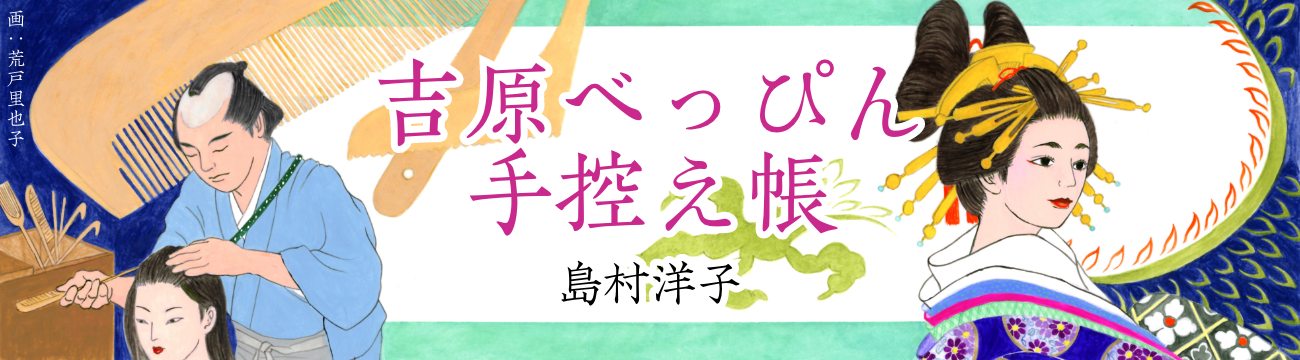第五話 夏ざかり宴競べ
島村洋子Yoko Shimamura
二
吉原の名店角海老楼(かどえびろう)にいる星形のほくろがある女郎と一度でもことをまみえれば運がつく、という評判を聞いて宮大工頭の惣吉(そうきち)は噂の女を買ってみたのだが、べつに博奕(ばくち)や富籤(とみくじ)が当たるわけでもなかった。
とはいえ逢瀬(おうせ)を重ねてみると件(くだん)のお歌(うた)という女は器量は一流とは言えないものの、気立てが良い上にかなり賢い女で深い情が湧いた。
同じことを思う男は惣吉の他にもたくさんいたようで、そうこうしている間に留袖(とめそで)新造だったお歌の人気は鰻登(うなぎのぼ)りとなり、珍しいことではあるがここに来て六歌仙(ろっかせん)という源氏名(げんじな)の花魁に格上げとなった。
そうなると花魁との初会のお目見(めみ)え、裏を返すと言われる二回目、そして馴染(なじ)みとなってお床入(とこい)りということの手順を踏まねばならなくなる。
しかし前からの馴染みである自分はそれらを省いても許されるだろうと勝手に考えていた惣吉だったのだが、どうやらそういうことでもないらしい。
ただ本当に初見の男がやらされるような祝言の真似事(まねごと)の大宴会はしなくても良いらしく、とはいえそれでもいくらかの先立つものがなくてはならない。
若い頃は親の仕事である表具屋の手伝いをしていたが、特別、手の器用な惣吉は期待をされて少しのあいだ、京で襖絵(ふすまえ)や掛け軸の修繕や金箔(きんぱく)貼りをしていた。
しかし結局は身分が問われる京(きょう)でのやり方に嫌気がさして一念発起、大きな寺の欄間(らんま)を作る見習い修業から宮大工になった。
いつのまにか芸道に通じている宮大工として評判になった惣吉には他の大工の倍を出しても良いという施主もいて、よく稼いではいたのだが相手が花魁ともなるとこれからの話は違ってくる。
せっかくここまでお歌と親しくなったのだから、その星形のほくろにあやかって富籤なりとも当たらないかと思って、まだ日のある吉原の町を歩いていた惣吉の目に不思議な物が映った。
夏の大きな雲を背にして、なにやら大店(おおだな)の二階の上に物干し台ともいえぬ面妖(めんよう)なものが組み立てられているのだ。
「ありゃなんだい」
惣吉が思わず声を出したら、そこに見覚えのある男の顔があった。知り合いの棟梁(とうりょう)のところで働いている富蔵(とみぞう)という大工である。
「お久しぶりでございます、旦那」
「おお、元気そうで何よりだな。ところであれは何を作ってるんだ? こんな大きな店の上に火の見櫓(やぐら)ってわけでもないだろう」
惣吉は行ったことこそないが、春日屋は名の通った名店である。
「いや、次の丑(うし)の日にある花火のためですよ。その日のためだけにあそこで宴(うたげ)をしたいらしいお大尽(だいじん)がいるんでさぁ、花魁のために」
「ほう、そりゃ豪勢なもんだなあ」
「なんでも花火を見たことがない花魁を不憫(ふびん)に思って大川の花火のときに一夜だけ、櫓を建てるんですと。終わればすぐにまた壊すんです」
風流な金持ちもいるもんだと感心した惣吉だったが、はてそういやお歌は花火を見たことがあるのだろうか、お大尽ほどの金はないが俺だって、出世祝いに何かしてやりたいものだと考えた。
お歌の馴染みの男の中には、花魁ともなってしまえば自分の手の届かないところに行ってしまった女だとあきらめてしまう者もいれば、出世魚ならぬ出世女郎とはゲンが良い、これからはもっと贔屓(ひいき)にしたいと言う者もいると聞く。
惣吉はお歌をあきらめられるほど割り切れるわけでもなく、かと言って花魁をずっと贔屓にできるほどの甲斐性(かいしょう)もなく、悩みが深まっていた。
どうせもういままでのようにしょっちゅう逢(あ)えなくなるのなら、最後に大川の花火のひとつも見せてやりたい。
自分は大工なので櫓を建てるのはたやすいことだが、そこで宴をする金となると心許(こころもと)ない。
しかし惚(ほ)れたお歌に祝いとしてぱっと面白いことをしてやりたい、と完成しつつある櫓を眺めているうちに惣吉にはある考えが閃(ひらめ)いた。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。