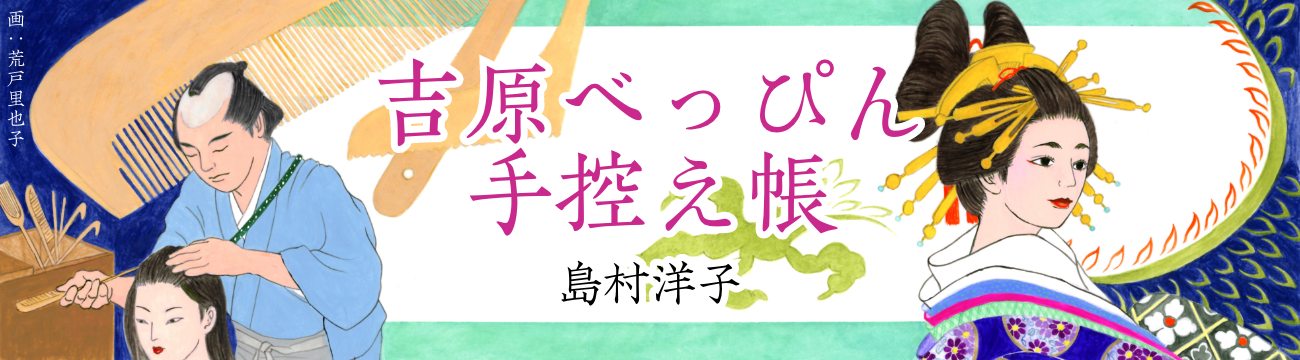第五話 夏ざかり宴競べ
島村洋子Yoko Shimamura
四
夕刻からお峰(みね)はその時が来るのを今か今かと待っていた。
外に出るのはほぼ一年ぶりのことで嬉しくもあったけれど、用心のために頭巾(ずきん)で口元まで隠し、母の陰に寄り添うように立っていた。
お峰は悪党にかどわかされて売り飛ばされ、苦労をなめたあと吉原に連れてこられて女郎となったのだが、九郎助稲荷(くろすけいなり)の神官の娘である母おつねの機転によって助け出されたのである。
とはいえ大門(おおもん)のそばの四郎兵衛会所(しろべえかいしょ)は人っこひとり見逃さないことで名を馳(は)せているし、逃げおおせた女郎は追手が草の根を分けても探し出す厳しい掟(おきて)がある吉原のことである。噂によると神隠しにあって、もうお峰はこの世にはいないのではないかということで店は落ち着いているらしいが、ゆめゆめ油断はならない。
お峰は慎重にも慎重を期して下総(しもうさ)でお鶴(つる)と名を変えて母や弟たちと暮らしていたが、この度、縁があり上州(じょうしゅう)草津(くさつ)の温泉地に嫁に行くことになった。
相手の桶(おけ)職人の佐吉(さきち)はお峰が女郎だったことをまったく知らず、さる旗本のお屋敷で数年女中をしていたという話を信じていた。
酒も博奕(ばくち)もせず、明るい気性の佐吉とはこの上なくいい縁だったけれど、それがいっそう嘘(うそ)をついているお峰の心を曇らせていた。
そんなお峰におつねは、
「おまえが望んで女郎になったわけでもないし、あたしが金のためにおまえを売ったわけでもないんだから、仕方のない災いに遭ったと思ってすべてを忘れればいいんだよ」
と励ました。
遠く上州まで娘を嫁にやるのは心配であったが、そこならば吉原通いなどした者はいないことを見越してのことであった。
なのに佐吉がこのあいだ急に「うちの村に嫁に来るとお鶴ちゃんはもう江戸に行くこともないだろう、おっかさんともなかなか会えなくなるべ。俺も村のもんへの土産話(みやげばなし)にもなるだろうから大川の花火が見たいのう」などと言い出し、断りきれずにずるずるとこの日を迎えてしまったのである。
これだけの人がいたら絶対に知り合いに会うだろうとお峰もおつねもヒヤヒヤしていた。
しかし皆は夜空ばかり見ていてすれ違う者の顔など気にしてはいない。
たまに下を見ている者があってもそれは銭でも落ちていないかとはいつくばっている子どもであったり、あちこちに出ている屋台を冷やかそうとしている者であったりと、誰もお峰の顔など見ていない。
佐吉は嬉しそうに義母になるおつねにもいいところを見せようと、
「なんでも欲しいものを言ってくださいよ」
などと言っている。
ほほに腫れ物ができたといって頭巾をかぶって下を向いているお峰にも佐吉は優しく接してくれていた。
そうこうするうちに乾いたパーンという音が空に響いて、花火が始まった。
見上げた空には四尺玉の大きな花火が輝いていた。
「うわあ、綺麗(きれい)ね、おっかさん」
お峰は花火の光に照らされて輝いている母の横顔に向かって声をかけた。
おつねも、口元が頭巾で隠れているがまだ若く美しい娘に微笑んだ。
思えば神社の神官の娘という良い身分に生まれた自分が駆け落ちなどという馬鹿げたことをしでかしたために、この娘にこれまでのバチが当たってしまったのだ。
どれほどの絶望の中で、娘が二年も過ごしたのだろうと思うとおつねはたまらない気持ちになった。
この度(たび)、上州に親類のいる近所の者が、縁を取り持ってくれた佐吉は心穏やかな性分でお峰も喜んでいるように見受けられる。
吉原の九郎助稲荷にいる父は「本当は自分が祝詞(のりと)をあげて神様のご加護をいただきたいところだがどこで誰が見ているかもわからないのでお相手の村でささやかに祝言を執り行うように」と言っていた。
先祖にも父にも申し訳ないことをしてしまった自分のせいでいろいろあったが、いまこの花火の下で本当に幸せだとおつねは夜空に手を合わせたい気持ちだった。
その時、
「あの、もしかして吉原でお目にかかった……」
と声を掛けて来る者があった。
お峰とおつねは震え上がった。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。