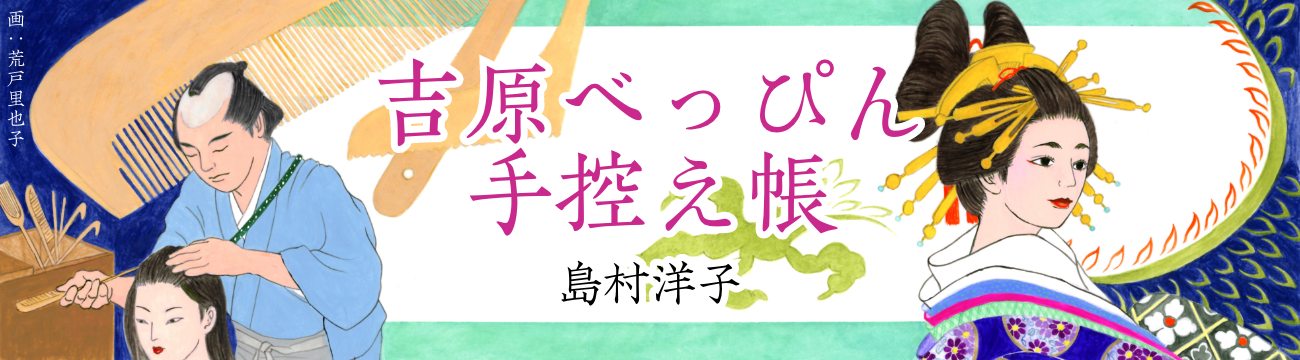第五話 夏ざかり宴競べ
島村洋子Yoko Shimamura
「ひとつお願いがあるんですが」
六歌仙は鏡越しではなくわざわざ清吉を振り返って言った。
「私にできることならなんなりと」
清吉はそう言い、中腰だった膝をついた。
「櫓の夜のことなんですが、せっかく龍田川さんを喜ばせようと春日屋のお客さんも考えてなされたことですのに、無粋にもこちらが真似のようなことをいたしまして本当に申し訳ないと思っております。亡くなった惣吉さんも祝いにとあちきを喜ばせようとしたことで悪気はなかったんだと思いますが、それにしてもみっともないことでありんして」
深々と頭を下げられた清吉は、
「六歌仙さんのお気持ちは間違いなく龍田川さんにお伝えしますよ」
と請け負った。
龍田川もそのお客も良い気持ちはしなかっただろうが、しでかした当の男が死んだとなればそんな了見の狭いことは言わないだろう。
なんとかとり持ってやりたいと考えながら角海老楼を辞した清吉は南部坂へ向かった。
そろそろ茶の湯の稽古の時分である。
冠木門(かぶきもん)を入り躙口(にじりぐち)をくぐって茶室に入ると、竹筒に黄味も鮮やかな菊が一輪活(い)けてあり、花火が終わったと思えばはやもう秋かと清吉は息をついた。
吉原も茶の湯も世間より少し季節を先取りする分、時の流れは早い。
花魁は客を選べるのだ、吉原には一晩で千両落ちるのだと華やかに噂されても所詮(しょせん)は買われた身、龍田川も六歌仙も客の都合で身の上が変わる。
いろいろなことに我知らず巻き込まれて難儀しているうちに月日ばかりが流れていく。
さてそのどちらが自分の妹なのかどちらも妹ではないのか、死んだ男はどうして何度も当たり籤を引けたのだろうか、それともあの斬った浪人のほうが悪いのか、清吉の胸の中は茶席というのに落ち着かなかった。
「あれ、お薄ですか」
清吉は出されたお茶に気づいて驚いて顔を上げた。
いつもならお濃茶が出るところであるのに。
「さっぱりしてはいかがかと思いまして。お悩みが深い様子とお見受けいたしましたので」
遠くに西陽(にしび)は感じられるものの薄暗い茶室の中、声の主の加賀見護久の表情はよくわからない。
「たしかに」
と、清吉は答えた。
「お軸でもご覧になりますか」
明るい声で護久は言った。
きっと自分を励ましてくれているのだろう、と清吉はありがたく思った。
近づいて見ると軸には赤と黄色の紅葉が一葉ずつ、絡まるように描かれていた。
「これは応挙(おうきょ)ですな」
清吉には見覚えがあった。
見覚えがあるどころかまったく同じものをさるお屋敷に出入りしている折に見た覚えがあった。
その頃は大店のご主人の月代(さかやき)を剃(そ)りに二月(ふたつき)に一度ほど出かけていたのだが、その時にこれは応挙だと教えられたのだ。
「よくご存知(ぞんじ)で」
「私はまったく同じものを昔、見たことがありますが、それがここにやって来たのですね」
「いや、それとは違います。これはこの家に伝わる古いものですから」
「では私がかつて見たものはこれの模写か何かだったのですね」
あの主人はたいそう自慢していたのに本物ではなかったのか、と清吉は思った。
「いや、それとこれとはきっと同じものです」
「え、どういうことですか」
清吉は思わず身を乗り出した。
同じ絵が二つ存在するとはいったいどういうことなのだろう。
「それは技術があれば簡単なことです」
そういう家元の口元を清吉は懸命に見つめた。
もしかすると二番富の籤が二つ存在することも同じ理屈かもしれないのだ。
「これは一流の表具師しか持っていない技術です」
「どういうことでしょうか」
はやる気持ちを抑えて清吉は尋ねた。
お茶を飲んだばかりなのに妙に口の中が渇いていた。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。