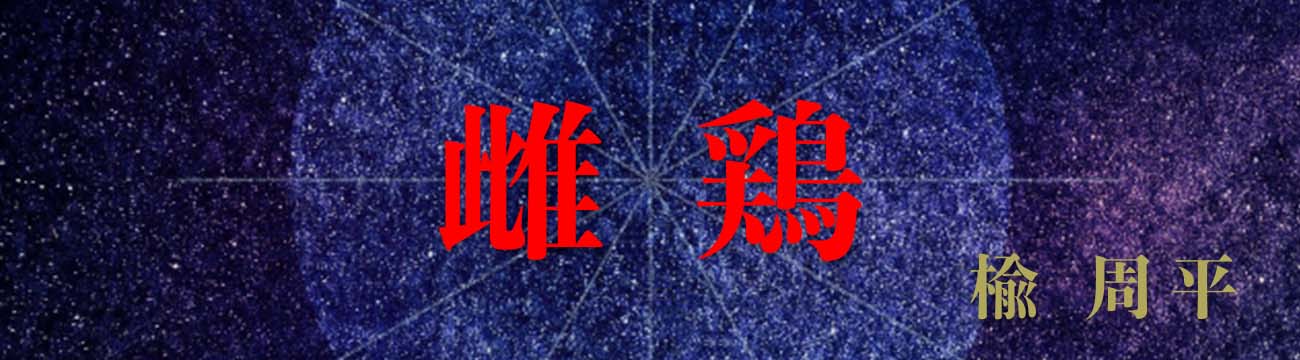第一章2
楡周平Shuhei Nire
「それで、お母さんの消息は分かったのか?」
鬼頭の問いかけに、貴美子は黙って首を横に振り、
「空襲から三ヶ月も経(た)っておりましたのでね。横浜の空襲では一万人も亡くなったと言いますし、中でも保土ヶ谷周辺は最も被害が大きかったところです。たった一日でそれだけの人が亡くなってしまえば、身元の確認どころではないでしょうし、焼夷弾の火力は、それは凄まじいものだったそうですので……」
「米軍の焼夷弾は半固形化したガソリンを使っているし、点火剤はマグネシウムだ。火力は強いし、落下してくる間に複数に分解するんだ。それが頭上から滝のように降り注いでくるんだからなあ……」
軍需物資の調達を業(なりわい)にしていただけあって、焼夷弾の仕組みを解説しながらも、鬼頭は気の毒そうに言い、「それで、お父さんは?」
と話の続きを促した。
「父の消息が分かったのは、それから暫(しばら)く経ってのことです。沖縄で戦死したと……」
「そうか沖縄でなあ……」
「父は横浜、母は生まれも育ちも東京の下町育ち。見合いで結婚したのですが、私が知る限りの親戚縁者は、空襲で亡くなってしまいましてね、それで天涯孤独の身になってしまったのです」
「兄弟は?」
「弟がおりましたが、三歳の時に病死しまして……」
「なるほど……。で、お前はそれからどうしたのだ」
「まず焼けた家の片づけを始めました。両親の思い出になるものが残ってはいないかとも思いまして……。焼け跡から使えそうな木材を見つけ、そこに莚(むしろ)をかけて、掘建て小屋を作りまして……」
話すうちに、当時の記憶が蘇(よみがえ)る。
真っ先に浮かぶのは、焼け跡から漂ってくる特有の臭いである。
木材、紙、そして何かの腐敗臭ででもあるのか、とにかく焼け跡はなんとも形容し難い不快な臭いを放つのだ。それは雨が降ると強さを増し、湿気と相俟(あいま)って、筵で覆われた狭い空間の中に充満するのだから堪(たま)ったものではない。
それでも何とか耐えられたのは、当時の日本国民の大半が、同じような境遇にあったからだ。
頭髪や衣服にシラミが湧くのは当たり前。動員先の工場では、同年代の女学生と寝食を共にしたが、寝床に入ればノミや南京虫の猛襲に遭ったのだ。
住居を失った国民は数知れず。夜になると主要駅の構内は、床に新聞紙を敷き横になる大人、戦災孤児たちで足の踏み場もない。彼らの着衣の汚れぶりは酷いものだし、足や腕には、幾層にも積み重なった垢(あか)がこびりつき、まるで全身が一つの瘡蓋(かさぶた)に覆われてしまっているかのような悲惨さだ。
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。