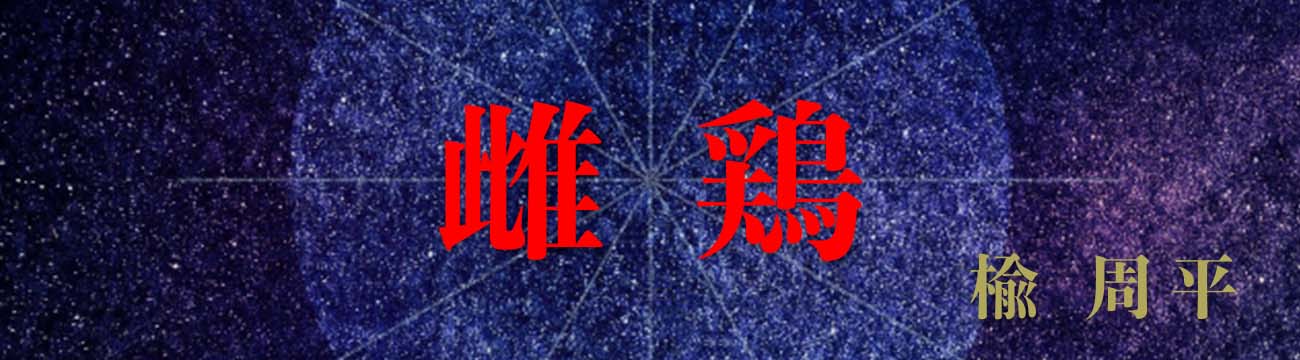第一章2
楡周平Shuhei Nire
貴美子は立ち上がり、
「そうですが……」
と答えながら、闇の中に目を凝らした。
「俺だよ、俺……。井出清彦(いできよひこ)だよ」
もちろん、清彦のことはよく知っている。
幼少期から頭脳明晰(めいせき)。小学校時代の成績は常に全甲。一貫して級長を務め、旧制中学から一高、そして帝大法学部に進んだ大秀才。しかも、貴美子が女学校受験を控えた直前の夏休みには、家庭教師を引き受けてくれたことがあったのだ。
「先生? 先生なんですか?」
年齢差もさることながら、その頃の名残もあって、貴美子は闇に向かって問いかけた。
「いい加減、その先生は止(や)めなよ」
闇の中から苦笑する声と共に、足音が聞こえたかと思うと、焚き火の明かりの中に清彦の姿が浮かび上がった。
その瞬間、涙が溢(あふ)れ出し、貴美子は号泣しながらその場にしゃがみ込んでしまった。
考えてみれば、両親も親戚縁者も全て亡くなってしまった今、動員先の立川から戻って以来、深く親交を結んだ人間と出会ったのは清彦が初めてだ。見知った人と再会できて、気が緩んだせいもある。安堵したせいもある。それに実のところ、貴美子にとって清彦は憧れの男性であったのだ。
もちろん、恋愛の対象としてではない。年齢差もあれば、将来を嘱望された清彦は、自分の手が届くような存在ではないと思っていた。それでも気になる存在であったことに変わりはないし、法学部に進んだ清彦は繰り上げ卒業で、兵役に就いたと母親から知らされていたこともある。
「だって……、だって、無事だとは知らなかったんだもの……。出征されたと聞いていたから、もしかしてと──」
「戦死したんじゃないかって?」
清彦は貴美子の言葉を先回りすると、「よく見なよ。ちゃんと足がついてんだろ? 幽霊なんかじゃないよ。俺はちゃんと生きてるんだ」
大口を開けて呵々(かか)と笑った。
貴美子は、しゃがみ込んだまま清彦の姿を改めて見た。
清彦が言う通り、足もあれば、顔にも体にも傷ひとつ見当たらない。
着用している国民服にしても、生地は緩んではいるが立派なものだ。
「命拾いしたんだよ。間一髪のところでね」
清彦は目元に笑いの余韻を残しながらも、感慨深げに言う。「俺、海軍に配属されて主計士官になったんだ。まあ、教育なんておざなりなもんで、早々に任官することになったんだけど、乗艦することになっていた軍艦が、内地に戻る間に次々に撃沈されてね。ずっと陸上勤務が続いていたんだよ。それでもいよいよ乗艦、俺もこれまでかって覚悟を決めたんだけど、横須賀を出て一日経ったところで、まさかの終戦ってことになったのさ」
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。