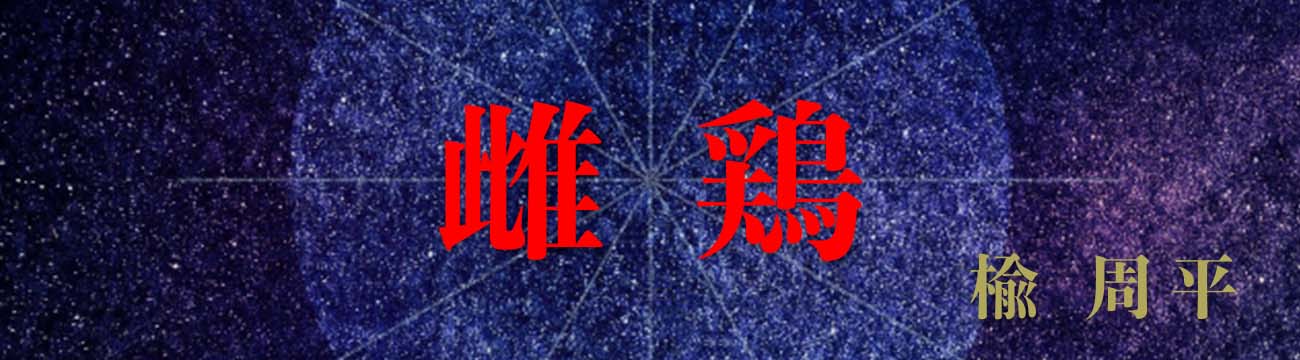第一章2
楡周平Shuhei Nire
5
昭和二十四年一月三日。
ツルと一緒に田町で始めた食堂は、開店直後から大繁盛した。
都市部での配給制度はまだ続いていて、食糧事情はまだまだ厳しい。そこで清彦が産地に赴き、直接仕入れた食材を使う食堂を開店したのだ。
粗末な代物には違いないが、他の店に比べれば格段マシだ。しかも、原価の安さを売値に反映させた。運び屋の摘発は頻繁ではあったが、三年も続けていると清彦も勘が働くようになったらしい。摘発に遭遇する回数もめっきり減ったおかげで食材の仕入れは順調で、その結果、「美味くて安い」とたちまち評判になったのだ。
食堂と言っても間口二間しかない小さなもので、供する料理も雑炊とスイトンの二品だけなのだが、それでも商売が繁盛すれば励みになる。
その日貴美子は年明け初日の営業を翌日に控え、午後から店の掃除と料理の仕込みに取り掛かっていた。
掃除は三人で、年末に入念に行ってはいたが、やはり年明け初日は新たな気持ちで迎えたいと思ったし、雑炊に用いる米は、この時期ならば前日に炊いておいても日持ちする。スイトンの生地だって、練り上げてからすぐには使わない。もっちり感を出すために寝かせるのだ。粗末であっても、こうした一手間を惜しまぬことが、繁盛に繋がるのである。
入念に竈(へっつい)を掃除し、炊事場の床やテーブルを磨き上げる。掃除が済んだところで、年末に包丁を研ぐのを忘れていたことを思い出し、貴美子は流しの下から砥石(といし)を取り出した。そして器に水を張り、砥石を浸したところで米を研ぎ、竈に火を入れた。
焚き付けは赤錆色(あかさびいろ)になった杉の落ち葉である。
竈の中にまず杉の落ち葉を敷き、その上に薪(まき)を置く。そしてマッチで杉の落ち葉に火を灯(とも)すと、白煙と共に炎が上がる。
薪に火が移り、火勢が安定したところで火力の調節に入る。最初は弱火で、そして強火で一気に炊き上げるのだ。
雑炊にするのだから、ここまで手間をかけずともいいのだが、清彦は明日からの食材の仕入れで、早朝千葉に向かった。正月でもあることだし、店に食材を持ち帰ったついでに、炊き立ての飯で夕食を共に摂ることになっていたのだ。
そうしている間に、砥石が十分水を吸う。
貴美子は包丁を手にすると、研ぎにかかった。
包丁は二種類。野菜を刻む菜切りと、主に鶏肉を処理する際に用いる、出刃を薄く、細くした形状の舟行包丁(ふなゆきぼうちょう)である。
最初のうちは難渋したが、上手くできるようになると、包丁研ぎは面白い。
研いでいる間は無心になれるし、刃と砥石の擦れ合う音が何とも心地よいのだ。それに、研ぎたての包丁の切れ味には快感を覚える。
どれくらい時間が経っただろう。
二つの包丁を研ぎ上げ、出来栄えを確かめようと、刃先に指を当てたその時、店の引き戸が音を立てて開いた。
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。