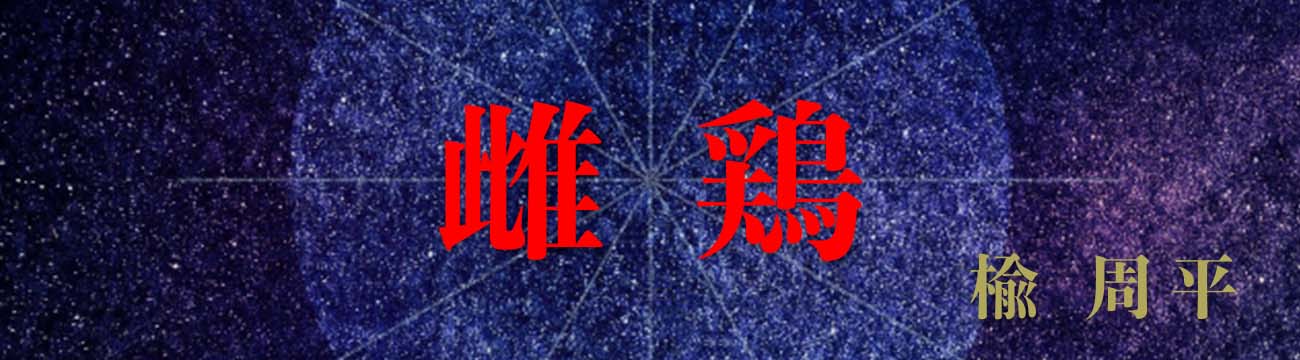第三章2
楡周平Shuhei Nire
「そやったら、七掛けで売らんで、うちとこがやればええやないかと思うでしょう?」
清彦の内心を見透かしたかのように、北原が問うてきた。
「そりゃそうさ。飯場に送り込めば、確実に儲けは膨らんでいくんだろ? 濡れ手で粟(あわ)ってやつじゃないか」
ところが北原は言う。
「さっき言うた餅は餅屋ってやつですわ」
「それ、どう言うことだ?」
「元本、利子を完済できなんだらどないなことになるか、重々承知の上で借りとんのです。飯場送りにされようと、娘を遊郭に売られようと、文句は言えへんのですけど、うちとこの社長は、そこまで鬼になれんのですわ」
「街金が、情けなんかかけたら舐(な)められるだけだ。それじゃあ、商売にならんだろう」
「情けをかけたら商売にならんちゅうのは銀行かて同じ。金貸しの基本中の基本ですわ。社長も重々承知してはるんですが、止(とど)めを刺すようなことは、ようやらん言うんですわ」
「何でまた?」
「直(じか)に聞いたわけではあらへんのですが、何でも社長がまだ小さい頃、親がこさえた借金の形に、姉さんが廓(くるわ)に売られてもうたらしいんです」
そう聞くと、北原の勤務先の社長がなぜ街金になったのか、その理由が見えてくる。
果たして北原は言う。
「金貸しが情けをかけたら務まらへんのは百も承知や。そやけどなあ、ワシにも娘がおるから、よう分かるねん。己がこさえた借金の形に娘を差し出す親は屑(くず)やと言わはったとかで……」
「娘?」
「一人娘がおりますねん。二十歳そこそこの……。社長、そら目に入れても痛くないほど可愛がっていましてね。年頃の娘を廓に売るとなると、お嬢さんの姿が重なってしまうんでしょうなあ」
「でもさ、債務者に年頃の娘がいれば、債権を売った先が廓に売るのは承知してるんだろ?」
「もちろんです」
「だったら、自分が直接手を下さないだけで――」
「結果は同じでも、餅は餅屋言うた理由はもう一つあるんですわ」
話半ばで遮った北原に向かって、清彦は問うた。
「それは?」
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。