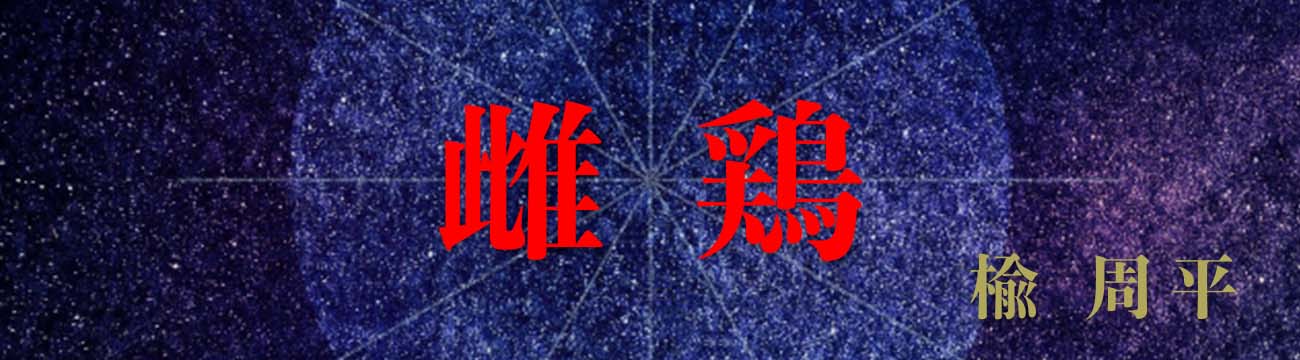第三章2
楡周平Shuhei Nire
東京を離れた頃には貴美子と二人、金に憂うることなく暮らせる程度の稼ぎがあればと思っていたのに、欲が湧いてきたのだ。まして、この手形金融は、清彦が考案したものなのに、莫大な利益の大半は、森沢の懐に入ってしまうのだからなおさらである。
実際、手形金融が軌道に乗るにつれ、清彦に対する森沢の厚遇は給与以外にも現れた。
尼崎の当初の住まいは、自前で一間の長屋を借りたのだったが、ふた月目には、小さいながらも新築の一軒家になった。もちろん家賃は森沢持ちである。さらに男の独り住まいは食事が大変だろうと、尼崎一帯の飲食店は全て淀興業へのツケで済むよう手配された。それも料亭だろうが割烹(かっぽう)だろうが構わない。勘定の制限も一切なしである。
もちろん、かかる費用を遥かに凌ぐ利益を齎(もたら)したからこその厚遇なのだが、手形金融は森沢の生活ぶりを一変させた。
一年も経った頃には、中古だが有馬温泉に総檜造(そうひのきづくり)の屋敷を購入。新車のベンツを駆って、妻のクメとミツ、そして清彦の四人で、週末をそこで過ごすのを常とするようになった。その際には、温泉街の高級料亭で贅(ぜい)を尽くした夕食を摂るのだったが、もちろん勘定は全て森沢持ちである。
もはや家族同然の扱い。清彦とミツを夫婦にせんとしているのは、明らかだったのだが、それも森沢が貴美子の存在を一切知らなかったからだ。
別に隠したわけではない。語る必要はないと清彦が考えたからにすぎない。
しかし、貴美子の存在を明かす機会はいくらでもあったのに、今に至るまでついぞ明かさずにきたのは、日々目の前を通り過ぎる大金。森沢の富が膨れ上がるにつれて暮らしぶりが激変していく様を目の当たりにしているうちに、己の決心が揺らいでいくのを自覚するようになったからだ。
そう、人間の信念や決意、価値観も時間の経過、身を置く環境によって変化するのだ。
才覚があっても、元手がなければ何もできない。元手があっても、才覚がなければ同じことが言える。二つの条件が揃って初めて莫大な富を掴むことができるのだと気がつくと、その才覚を森沢のために発揮してしまったことを清彦は後悔するようになった。
日々目の前を通過していく莫大な金の権利は俺にある。
森沢は、ただの金主に過ぎない。
ならば、どうやってこの商いを、金を自分の物にするか……。
方法は一つしかなかった。ミツと夫婦になることだが、それでも清彦は自ら切り出すことはなかった。
その時がくるのは時間の問題だと確信していたし、その後のことを考えれば、持ちかけた者、持ちかけられた者、どちらが優位に立つかは明らかだからだ。
「清彦君、ちょっと話があるんやがね」
改まった口ぶりで、森沢が切り出してきたのは、手形金融が始まって一年半ほど経った頃、有馬温泉の別荘でのことだった。
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。