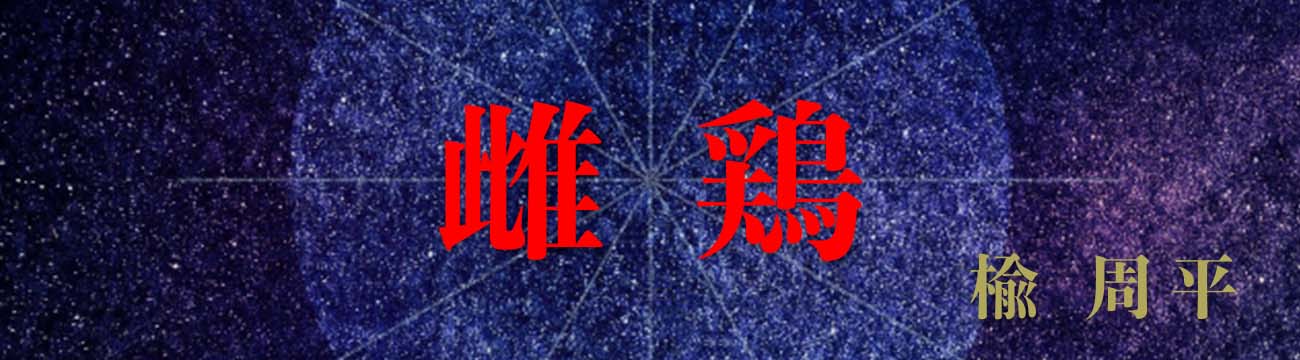第三章2
楡周平Shuhei Nire
4
清彦が考案した手形金融は、自身の予想を上回る反響を呼んだ。
戦争は命と同時に、物資の消耗戦でもある。中でも燃料と並んで、絶対的に必要不可欠な物資は原材料、特に鉄である。
戦前から製鉄所を中心に栄えた尼崎には、中小の金属加工会社や機器メーカーが数多く存在しており、戦中の空襲で打撃を被った工業地帯の一部も、終戦から四年も経(た)つと戦禍の痕跡が失せるまでに復興を遂げていた。
そこに、朝鮮戦争という特需が舞い込んだのだ。
増産要請に応えるためには生産機材の増設、人員の増強が必要不可欠だ。しかも戦(いくさ)に休みはない。かくして資金需要は増すばかりとなったのだが、発注元からの支払いはもれなく手形である。
支出と入金が同時期であれば資金繰りに困ることはないのだが、万事において力のある者が優位に立つのが商売だ。事業規模が小さくなればなるほど、取引の条件は厳しくなり、逆に手形の決済までの期間は長くなるのだから、当座の資金繰りに窮する会社は数知れず。そんなところに、日歩五銭で融資を受けられる話が持ち込まれれば、飛びつかないわけがない。
融資依頼は次から次へと舞い込んでくる。返せる当てがあっての借金ゆえのこともあったろうが、銭というもはや使われなくなった通貨単位のせいもあったに違いない。
しかし、それは錯覚というものだ。
なぜなら、二枚の手形に発生する利子を合算すれば日歩十銭。百万円の融資を受ければ、利息は一日千円にもなるからだ。
高卒公務員の初任給が三千八百五十円、大卒は四千二百二十円程度であったから、一週間で七千円。ひと月ならば約三万円。中間値で計算すると七人分の初任給に相当する額である。
もちろん、借り手は金ができ次第、直ちに返済してくるのだが、好景気の最中とあって、受注は拡大する一方だ。当然原材料の仕入れ代金、人件費、燃料、電気等々の固定費も嵩(かさ)むばかり。しかも、これらの支払いは待ったなしだ。
かくして、経営者は常に資金繰りに追われることになり、この清彦が考案した手形金融は、淀興業に莫大な利益をもたらすことになった。
実際、清彦の初任給は月額三千五百円。修業の身とはいえ、帝大出の給与としては驚くような低賃金であったが、それも二ヶ月ばかりのことで、商売が軌道に乗るや一万円が二万円になり、半年もすると月額五万円にもなった。
それでも、淀興業がこの手形金融から得た利益に比べれば、微々たるものであったのだが、森沢にとって清彦は、突如舞い降りた福の神。是が非でも手元に置いておきたい人間と映ったのは間違いあるまい。
- プロフィール
-
楡 周平(にれ・しゅうへい) 1957年岩手県生まれ。米国系企業在職中の96年に書いた『Cの福音』がベストセラーになり、翌年より作家業に専念する。ハードボイルド、ミステリーから時事問題を反映させた経済小説まで幅広く手がける。著書に「朝倉恭介」シリーズ、「有川崇」シリーズ、『砂の王宮』『TEN』『終の盟約』『黄金の刻 小説 服部金太郎』など。