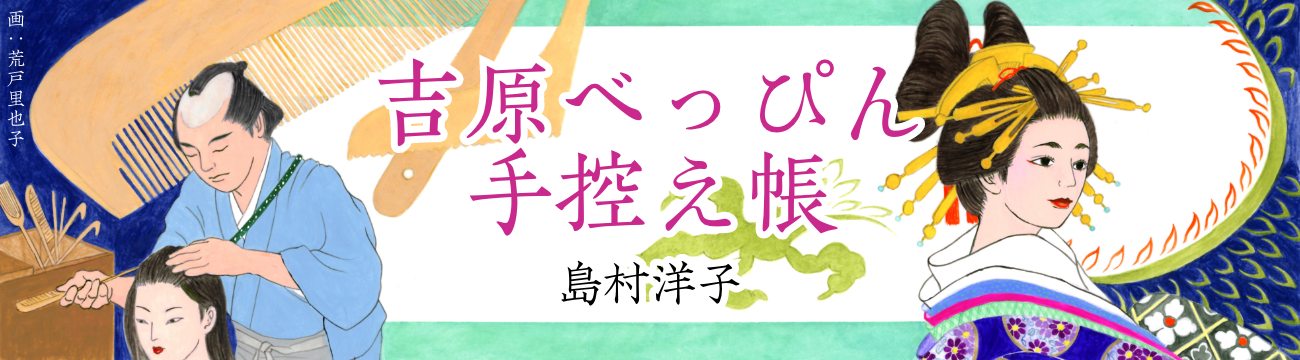第四話 星形のしるし
島村洋子Yoko Shimamura
持ってきた練り切りは桜の花びらを模した薄い色で、眺めていると心が少し晴れたがそれとて慣れた味に違いない。
「これは下品な物になりますが、娘が摘んだもので作りました草餅でございます」
「おお、それはありがたい」
正式な茶会には出せないが、餅やら団子やらはなぜか心が和む。
色や形で無理矢理に先取りの春を表現したものより、噛(か)んだ時に鼻から抜ける青臭い蓬の香りこそが本当の春そのものなのだ。
そしてこの小さな茶室ではなく、一歩出たところにある広い世の中が本当の人生なのだ。
それを実際に味わいたいと護久は兼ねてから願っていた。
菓子屋の心遣いが嬉しく、護久は礼を言った。
流行り病で急に死んだ先代の代わりとなればと精進したのも束(つか)の間、退屈で仕方ない毎日に飽き足らず瓦版(かわらばん)を買い求めてみたり、井戸端の女たちの噂話に耳をそば立てたりしていた護久だった。
家元家元と下にも置かれずちやほやされては来たが、その実、生来の下戸で酔って明るく過ごせるわけでもなく、かと言ってしっかりとした芯のようなものがあるわけでもない我が身より、市井の人々のほうが人生を謳歌(おうか)しているのだという憧れがあった。
その焦りに似たものを解消できる「何か」を探していた。
そしてその「何か」はついに日本橋から稽古に来ている海苔屋の倅の愚痴の中に見つかった。
代々、田中屋忠左衛門を襲名するその海苔屋は日本橋のたもとでもひときわ大きな店構えで、江戸に生まれた者ならば誰もが一生に一度は口にする海苔を商っている。
その倅の新兵衛は目元涼やかな美丈夫なのだが、父の忠左衛門に言われて、嫌々ながら護久のもとに稽古に来るようになった。
父の忠左衛門は長いあいだ、護久の父に稽古に通って来ていた。
大きな商いをしている田中屋なので茶会や句会に呼ばれることも多く、当主はあらゆる教養を求められる。
茶の湯に限らずいろいろな習い事をせねばならなかった忠左衛門は、北千家の家元が護久に代わってからも幾度か稽古には来たが、ある日を境に現れなくなったのでこちらから出稽古に向かおうかと思っていた矢先、倅を寄越すようになった。
おまえの水準ではうちの倅程度で充分である、と言外に示されたようで面白くなかった護久だったが、それでも愛想の良い倅の新兵衛に丁寧に稽古をつけていた。
「吉原に通いつめですか」
新兵衛の言葉を鸚鵡(おうむ)返しにしながらも、護久はいま聞いたことを信じることができなかった。
なんでも新兵衛の父である忠左衛門は花魁の虜(とりこ)となり、三日に上げず吉原に通っているというのだ。
真面目一方にしか見えなかったあの忠左衛門に何があったのだろうと護久は興味を持った。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。