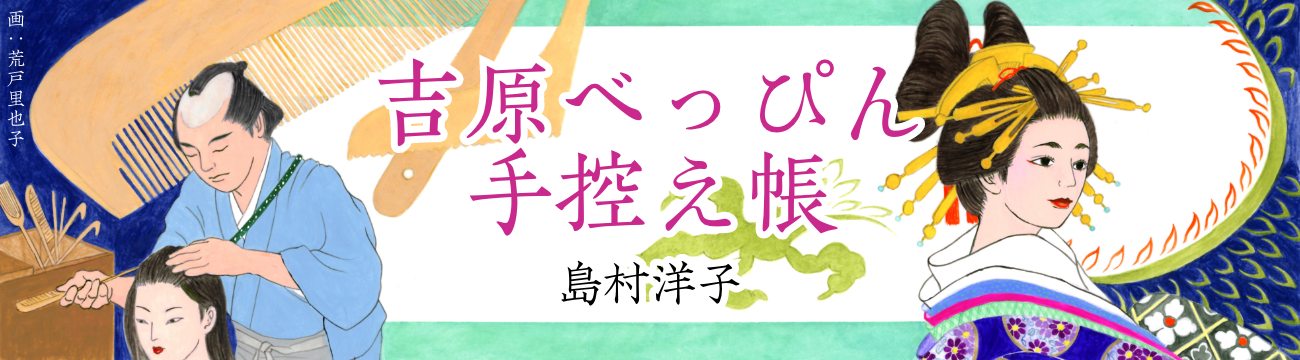第一話 金泥の櫛(くし)
島村洋子Yoko Shimamura
一
空を見上げると白い鱗(うろこ)がくっついたような長い雲が見えた。
まるで龍が自分に付いて来ているようだと清吉(せいきち)は思った。
湯島(ゆしま)近くで三年髪結いの修業をし、いまでは師匠を凌(しの)ぐ腕と言われているので独立をすすめてくれる人もあったり、師匠にもいずれはここを任せるとまで言われた清吉だったが、首を縦に振らなかったのには理由があった。
それは子どもの頃に離ればなれになった双子の妹を探しているからである。
妹の記憶は襟足に星形のほくろがあることと、お鯉(こい)という名前だけである。
子どもの頃はそっくりと言われた兄妹だったらしいけれど、もう二十歳(はたち)に近づく最近では面変(おもが)わりしてしまったかもしれない。
もう一度空を見、息をついた清吉が心を整え、吉原(よしわら)の大門(おおもん)をくぐろうとした時、突然大きな声が聞こえた。
「土左衛門(どざえもん)だ、土左衛門、土左衛門が見つかったぞ!」
わさわさと人が集まってきていた。
お歯黒どぶと言われるこの堀には店を抜け出そうとして転落する女郎や酔っ払って溺れてしまう客などがいたが、土左衛門というからには何日かたって発見されたものだろう。
喧嘩(けんか)の挙句に刺されて突き落とされたものかもしれない。
清吉はむしろに乗せられた土左衛門に近づいて行こうとしたがすぐにやめた。
何度かここに来たことはあるけれど、まさか働きに来ることになるとは思わなかった。
とはいえ女を探すのは、結局ここしかないのかもしれないとも思った。
背中越しに「見覚えあるかい」「誰なんだい」という野次馬の声が聞こえていた。
「なんでも菊の柄の漆の櫛を懐に抱いていたらしい」「風流な話だ」などと髪結いの清吉にとっては気になる話でもあったが、一度この大門をくぐって職を得たが最後、つまらないことには興味を持たないことだと清吉は自分を戒めた。
たったひとりの大事な妹が売られていると想像するのは気持ちの良いものではなかったけれど、親のない子の行きつく先はそう多くはない。
そうなっているとしたら救い出せるかもしれない。
妹が苦界(くがい)にいないならそれも良し、人の集まるところゆえに噂(うわさ)もなにかしら入ってくることもあるだろうと思い決意した清吉だった。
決めたからには吉原一の髪結いにならなくてはいけない。
金に糸目をつけない人々を夢中にさせるその女たちの髪を触るのは不安でもあり、喜びでもあった。
まだ昼前というのに吉原は出入りの商人(あきんど)も多く、活気に満ちていた。
食い物を運んでいる者も花を抱えた者もすべては「夜」のために生きている。夜の夢のために。
清吉がこれから世話になる髪結処亀屋(かめや)は遊女買いのお客が歩く表筋ではなく裏手にある。
湯島で聞いてきたとおりにどんつきを折れて小さな「亀屋」と書かれた看板を見つけて清吉は裏から静かに店に入った。
「ごめんなさい、湯島の『正屋(まさや)』からやって来ました清吉でございます。お世話になります」
清吉は頭を下げたまま、言った。
一瞬の沈黙のあと、
「聞いているよ、ちょいとお待ちなさい」
喉の奥に砂でも撒(ま)いたようにザラついた年増(としま)の女の声がついたての向こうから聞こえた。
規模は小さいけれど、店内すべてが几帳面(きちょうめん)に整えてあるのが裏手からも感じられて清吉は好感を持った。
店に充満した椿油(つばきあぶら)の甘く香ばしいなんとも言えないいい匂いが、ここは流行(はや)っている髪結いなのだと感じさせる。
ついたての向こうに誰かがいた。
多分、店まで髪結いを呼べない身分の女郎なのだろう。
清吉がやって来たためか客の女の声は低くなったが、なにやら相談めいたことをしていたらしい。
「ではよろしくお願いします」
女の声は若かった。
「じゃあ、お美弥(みや)ちゃん今日もお稼ぎくださいね」
その言葉に女は立ち上がり、こちらを向いた。
まだ幼さの残る可愛(かわい)い娘だった。
きまり悪そうに微笑(ほほえ)んで清吉に会釈した。
なんとも言えない愛らしい顔立ちである。
この娘は売れるだろうと清吉にはすぐにわかった。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。