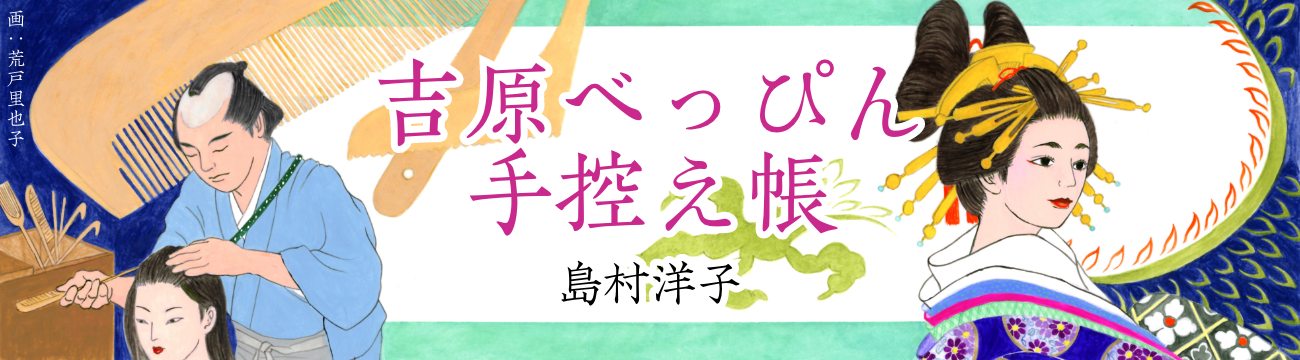第四話 星形のしるし
島村洋子Yoko Shimamura
十一
茶道北千家の若き家元である加賀見護久は今日も庭を掃き清めながら考えていた。
こういうことは弟子にやらせれば良いのだろうが、護久は炭鉢の並びや緑の葉の一枚一枚の位置まで自分でやりたい性質(たち)である。
この前、草餅を持って来てくれた出入りの和菓子屋が今日は柏餅を持って来た。
「また下品なもので恐縮でございますが、そろそろこんな季節でして」
「そうですね、菖蒲(しょうぶ)も楽しみですなあ」
護久は紫の花がことのほか好きだった。
「つかぬことをお尋ねいたしますが家元は一昨日、葛西村(かさいむら)に稽古にお出かけになりましたか」
額の広い菓子屋の顔をしげしげと見ながら護久は首を振った。
「葛西村? そんな遠いところまでは頼まれてもお断りしますなあ」
「やはりそうでございましょうな。では小岩村(こいわむら)のほうに五日ほど前にお見えになられましたか」
「いやそれもございません」
何を言われたのかわからなかった。
「いえね、その日に北千家の家元加賀見護久様と名乗る茶道の家元がやって来て、かなりの人を集めてお稽古をしたらしいのです。そんな遠いところに家元がお見えになるわけはないと思いまして。もしお稽古があるならうちのお菓子を使っていただけるでしょうし」
「つまり偽者が出たということですな」
護久は笑った。
自分になりすましてどうするというのだろう。
たしかに名の通った流派なので、そこそこ人は集まり金にはなるかもしれないが大儲(おおもう)けというわけでもないだろうし、ある程度の知識がないと家元のふりはできないし、何しろこうして直ぐに露見するから長期に稼げるわけもない。
「いったいなんでそんなことをするんだろう」
護久は独りごちた。
「さあ、私にはわかりかねますがなにかこう、家元様になってみたかったのではないんですかねえ。知らない土地で自分とは別の偉い人になって大切にされたいような」
菓子屋も遠い目をしてつぶやいた。
「たしかに」
護久は水を含んできらきらと輝く苔を見つめていた。
自分も別の誰かになりたかったのかもなあ、と。
海苔屋の倅たちの役に立ちたいだけではなく、吉原で綺麗どころをはべらせて酒を呑むような真似事をしたかったのかもしれない。
自分のような代々の家元ではなく、自身の甲斐性(かいしょう)で大金を稼ぎそれをぱっと使う男の真似を。
「調べて突き出してやりましょうか」
と憤っている菓子屋に護久は言った。
「うちの宣伝をしてくれているんでしょう、ほうっておきましょう。偽者というのは長続きするものでもないですし」
「さすが、家元はお優しくしかも大人物でいらっしゃる。いやこれは失礼を申し上げました」
そう言って頭を下げる菓子屋の言葉にうなずきながら、護久は蓬餅をくれた美しい花魁の姿を忘れられずにいた。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。