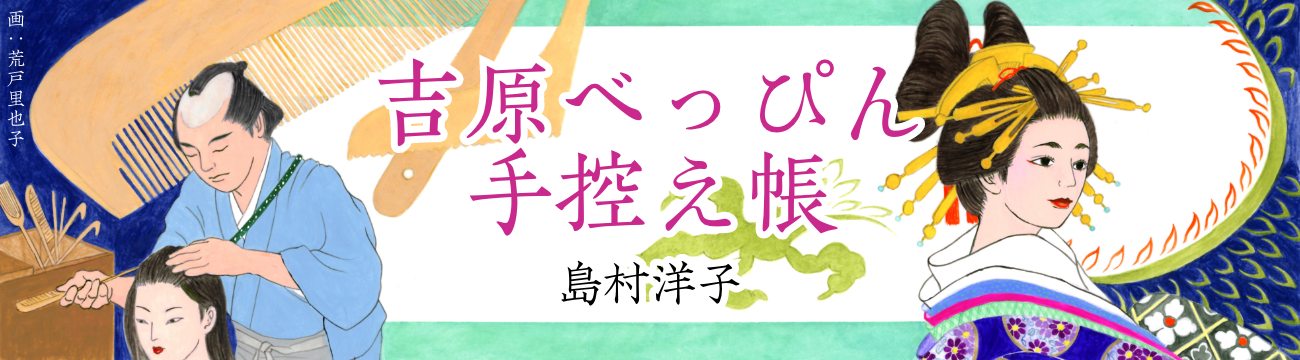第三話 絵馬の花嫁
島村洋子Yoko Shimamura
五
ぼんやりと明るい大きな広間の奥には金屏風(きんびょうぶ)が立てられていて、二列にずらりと並んだ箱膳の上には紅白の水引きが結ばれた鯛(たい)が置かれていた。
いくら狸といえども、こんなに手のこんだことをするだろうか、と寅吉は不安になった。
自分の頭がどうにかなってしまって夢もうつつも一緒になってしまい、この世のものではないものを見ているのに違いないと思いはじめていたからである。
二十人はいるのだろうか、箱膳の前には晴れ着や紋付で祝言に参列する格好をした老若男女が座っている。
ただよくある祝い事と違うのは誰一人として笑顔の者はなく、何やら神妙な顔をしていたことだった。
狐(きつね)の嫁入りという言葉は耳にしたことがあるので、もしかするとこれは、狸の仕業ではなく狐に化かされているのだろうか。
そう寅吉が考えはじめた頃、
「花嫁のおなりー」
と告げる声が奥のほうから響いて来た。
その声とともにどこからともなく女が数人現れて、法事に坊主が座るような立派な錦糸の座布団を何枚も持ってきて寅吉の隣に積み上げた。
いったい何が始まるのだときょろきょろしている寅吉のもとに紋付を着た屈強な男が、綿帽子に白無垢(むく)の花嫁を抱きかかえて入って来た。
真っ白な顔に下唇にだけ紅を差した花嫁は、透き通ったように見えて美しかったが、どういうわけか熟睡していた。
積まれた金色の大座布団を背もたれにして、花嫁は座らされている。
綿帽子をかぶったままでがっくりと後ろに折れた首は力がなく、顔は仰向(あおむ)けになっている。
目を開けたらなかなかの美人だろうな、と寅吉は考えた。
腹のあたりで組まされた指も白く長く、苦労知らずの箱入り娘として育ったのだろうと思わせた。
思えば自分はこれといった女と知り合うこともなく、流れ流れてここまで来た。
蕎麦を食ったあと、道で薄赤い書状を拾っただけでこんな大ごとに巻き込まれてしまっているが、これほどの屋敷を持っている分限者の娘を嫁にもらえるのだったらこれはこれで身に余る幸せではないか。
何が起こっているのかはわからないが、これを奇貨として幸福になればいいのではないか。
寅吉がそう思い始めた頃、さっき道端で丁寧に挨拶をしてきた身なりの良い初老の男が立ち上がった。
いつのまにか紋付羽織り袴に着替えている。
その瞬間、木遣歌がぴたっとやみ、ざわざわとしていたあたりに静寂が訪れた。
「本日はお日柄も良くおめでとうございます。手前はこのたび、仲人(なこうど)を申し付けられました大塚庄兵衛(おおつかしょうべえ)にございます」
しーんとした座敷はお通夜のようである。
「西小松村(にしこまつむら)の仙右衛門(せんえもん)様のひとり娘、おうたさんと白山村の寅吉さんのご縁、相調いまして本日の祝宴となりました。どなた様も遠慮なく酒を呑(の)み、ご馳走(ちそう)を召し上がりまして、若い二人のこれからを祝福してくださいまし」
その言葉を手始めに皆がめいめい祝い箸を手にした。
しかし嬉(うれ)しそうな者はいないし、寅吉たちが座っている高砂(たかさご)の席にお銚子を持って近づく者もいない。
ただ静かに粛々と宴は進行している。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。