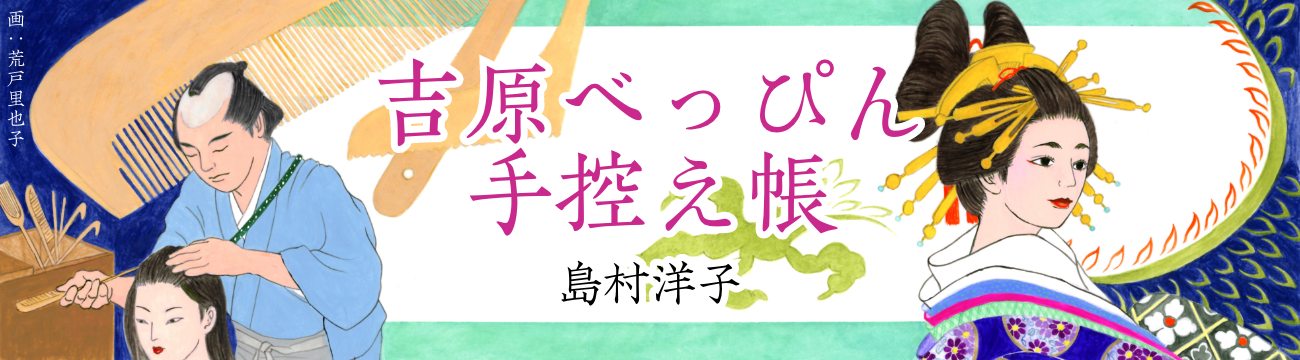第三話 絵馬の花嫁
島村洋子Yoko Shimamura
六
湯島天神へ続く右手の道は土産物屋や茶屋が並び賑(にぎ)わっているのだが、東八幡宮へ向かう左手の道はだんだんと藪(やぶ)になり昼間でも暗い。
早足で清吉はその暗い道を歩いていた。
この前に来た時も誰ともすれ違わなかったが、今日も人っ子ひとり犬すらも歩いてはいない。
まあ死んだ人の親族は寺に行って供養するのがふつうであり、生きていた時の夢を叶えてやろうとするのはいくら身内の情と言ってもちょっとおかしな話であるから賑わうはずもないのだろう。
若くして命を絶たれたものを不憫と思う身内の悲しい心がこの場所をいっそう寂しくしているのかもしれない、と清吉は思った。
東八幡宮は神職が常時いるような大きいところではなく、森閑として音がない。
賽銭を入れて鈴を鳴らして手を合わせた清吉が見上げると例の絵馬が暗がりにぼんやりと見えた。
団子を食いながら旅をしているような呑気(のんき)な絵面の絵馬もあったが、この絵の男は生きているうちに伊勢参りでもしたかったのだろう。
その楽しげな絵馬の隣にくだんのものがあった。
丑蔵二十歳と書かれた紋付羽織り袴の男の横にいる花魁龍田川そっくりの花嫁は心なしかこの前、見た時より正気がない。
絵とはいえども生きている人間さながらの生き生きとしたものが漂っていたのだが、今日は隣にいる花婿と同じように見えた。
これはまずい、と清吉は直感した。
とにかくよじ登ってあれを取り外すことが先決かと考えたが、いくら無人とはいっても勝手に中に忍び込むことはできないだろうから、とにかく事情がわかるものに立ち会わせるか何とかして修繕を装い、持って帰って焼いてしまおう。
清吉は寂れたあたりを歩きまわってみた。
裏に回ると見逃してしまいそうな小さな団子屋があった。
清吉はとりあえず団子を頼み、落ち着いた様子をして熱い茶を呑んだ。
あばたのある中年の女が、
「お詣りですか。ご苦労様です」
と言った。
清吉は、
「あっしは絵描きなんですが、お恥ずかしい話、ここのところ仕事に恵まれませんで、なんか御用はないかとあちこち探しておりまして。絵馬の仕事でもいただけないかと神社を主に回っています。なんでもここの八幡様の絵馬には大きいものもあると聞きまして。でも神主様はお見かけしませんでしたがどこにいらっしゃるんですか」
と困ったような声で言った。
「あらまあ、絵描きさんなんですか、それはそれは。いえね、ここの神主様は浅草のほうの人で二のつく日しかこちらへは見えないんですよ。ただここに奉納する絵は病気が治ったお礼や七福神の絵みたいにふつうの神社によくあるものじゃなくて、ちょっと訳ありのものですから、神主様はあまりご存知ではないんじゃないですかね。絵をお願いする方は神主様というよりはどちらかというとお坊様に紹介されるのかもしれません」
「はて、お坊様というのはどういうことですか」
清吉はお茶をすすったあと、ひと息ついて言った。
「いえね」
少し声をひそめて女は言った。
「この八幡様はこの世のことを叶えてくれるのではなくて、亡くなられた方のあの世での望みを叶えてくださるんですよ」
「ええ!」
清吉が自分でもどうかと思うくらい大袈裟(おおげさ)に驚いて見せると女は乗ってきた。
「いや、こないだもね、甥(おい)を若くして亡くされたと言う初老の女の人が甥御さんの冥土での婚礼の大きな絵馬を奉納されましたよ。ものすごい綺麗(きれい)な花嫁さんの姿を添えて」
「ああ、あっしもそれをさっき見ました。綺麗でしたね。ああいうのは何かお手本があるんですかね。頭の中で思いついた女にしてはいやにこう、生々しいというか、ちょっと感心しましたもんで」
「さあ、どうなんでしょうね、あんなべっぴんさん本当にはいないでしょうからね」
首を傾(かし)げる団子屋の女に、それが吉原にはいるんでさあ、と言いたい清吉だったが、
「いるんならお目にかかりたいもんですね」
としらばくれてうなずいた。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。