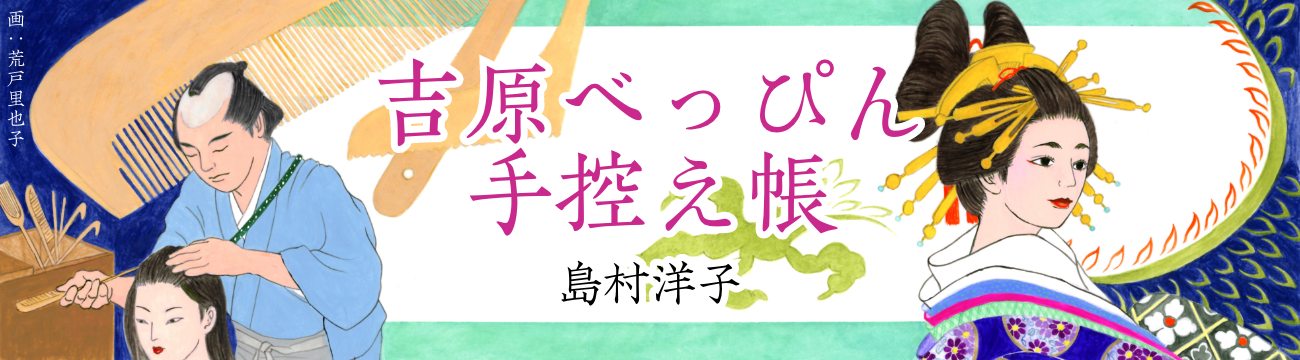第三話 絵馬の花嫁
島村洋子Yoko Shimamura
十五
大塚初右衛門に呼び出されたお糸はあんぐりと口を開いて絵馬を見上げた。
堂内の中は昼の日なかでも薄暗かったがそれでもはっきりとわかる。
甥の丑蔵の隣にいるのは自分が奉納した龍田川ではないことが。
「これは」
一津星ではないか。
お糸はすべてを一瞬で理解した。
伏せっていた龍田川が突然元気になったのも、そして一津星が急に熱を出したのも、すべてはこれのせいなのだ。
そして自分が秘密に奉納したこの絵馬のことを何故(なぜ)だか知っている者がいる。
確信は持てなかったけれど春日屋の者で、自分のことを良く知っていないとこんなことはできないだろう。
万事を取り仕切ってくれたこの大塚初右衛門も他言はしていないだろうし、自分の商売を詳しく知っている者というのは限られてくる。
これが天網恢々(かいかい)疎(そ)にして漏らさずというか、神はお見通しということなのだろうか。
そう思って改めて見てみるとなんとなく絵の中の丑蔵も不機嫌そうである。
「と、とにかくこれを下ろしてください。焼いて始末してください」
初右衛門は訝しげだったが、そもそも生きた花魁を描いてくれというのが土台無茶なことだったのだ、と始末にかかる金を少し受け取り、魂でも抜かれたようにふらふら歩いて行くお糸の後ろ姿を見送った。
十六
「へえ、お糸さんが急に。またどうしたことでありんすか」
突然、遣り手ばばあのお糸が生地の辰巳村に帰ったと聞いて龍田川は驚いた。
「さあ、私が虐(いじ)め過ぎたからかもしれませんなあ」
冗談めかしてそう言う遣り手ばばあの先輩おきぬの言葉に龍田川は笑った。
「真面目(まじめ)な話、たったひとりのお身内を亡くされたらしくて、思うところがおありだったそうですよ」
「まあそれは気の毒に」
そうは言ったが、考えてみれば龍田川にも身内はいない。
「まあ借金もなくなって、最後は外で生きていきたいという気持ちもわかりますわなあ」
流行りの風邪に過ぎなかったのか一津星も回復して春日屋の花魁ふたりは元気に仕事を勤めている。
清吉は何もなかったように今日も龍田川の髪を結いあげている。
「ああ、あっしも熱が出たら大雪の日の夢を見ますよ。不思議ですなあ」
そう言う清吉の声に、
「そうでありんしょう? 不思議なことでありんすなあ」
と応じる華やいだ龍田川の声を聞きながら、おきぬは花魁はもしかすると清吉が好きなのかもしれない、ふたりあの絵馬のように婚礼衣裳で並べばどんなにお似合いのことだろうと考えていた。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。