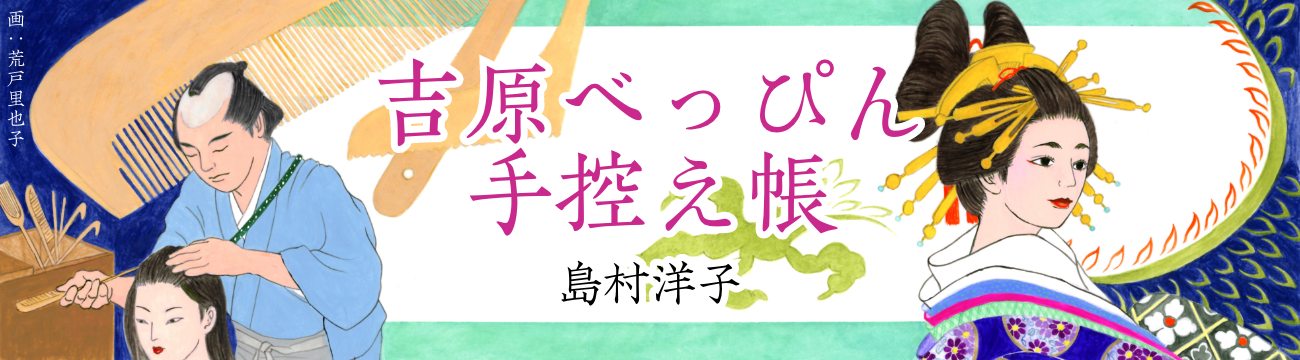第三話 絵馬の花嫁
島村洋子Yoko Shimamura
白山村の寅吉と、仲人が言ったということは自分を誰かと間違えて拉致してきたのでないことは確実である。
しかし寅吉の親元には金も力もないし本人もただの雇われの身であるから、こんな立派な家の主人が美しい娘を嫁がせる理由もない。
寅吉の容姿が役者のような色男で江戸中の娘たちにきゃあきゃあ騒がれているのならまだしも、悲しいかなそういうこともありはしない。
いま行われていることは間違いでもなく、かと言って正しくもないのだ。
「ちょ、ちょっと厠(かわや)に」
と寅吉は目の前でかいがいしく料理を運んでいる女に囁(ささや)いた。
女は困ったように仲人の大塚庄兵衛を見上げたが、庄兵衛はうなずいた。
「さ、さ、こちらでございます」
足元を照らす提灯を持った女中に廊下を先導されながら、寅吉は歩いていった。
座敷も立派なら廊下も立派で、いったいどこまで続くのかと不安になるほど長く歩いた端にこれまた広い廁があった。
放尿しているとこれは夢ではなく現実だという感じがありありと湧いてきた。
自分は確かに花婿なのだ、覚悟を決めて祝宴を楽しむのも一興ではないか、と寅吉がそう決意した時、誰かが入ってきた。
若い男だった。
薄暗い廁で寅吉と目があってしまった男は困ったような表情を一瞬見せたが、すぐに、
「この度はおめでとうございます」
と言った。
男はどう見ても狸でも幽霊でもなく、この世に生きている人間に見えた。
事情を訊(き)けばすべてわかるに違いない、と寅吉は男に、
「あの」
と口を開いたが、男はそれを制するように、
「あっしは何も知りゃあしません」
と言った。
男の目つきは鋭くなった。
「でも」
とすがるように続けた寅吉に首を横に振った男は、低い声で、
「出されたものは何も食べちゃあいけませんぜ。戻って来れなくなりますから」
と早口で言った。
それだけが精一杯だと言ったふうに男はもう寅吉のほうを見ようとはしなかった。
「あの、もし。戻れなくなるとは何処(どこ)から」
寅吉をここまで案内してくれた女中の呼ぶ声に、寅吉は慌てて廁を出た。
座敷に戻り奇妙な宴会のあいだ、寅吉はうまそうな料理に箸は付けなかったが酌をされるまましたたかに呑み、だんだん酔って来た。
誰かがいい喉で聞かせる長持歌が心地良く、眠ってしまいそうになった。
うつらうつらしながら、自分は本当に変な夢を見ているのだなあと寅吉は思った。
思いながら、さて夢であっても自分の妻になる女をじっくり見てみようと綿帽子をかぶった花嫁のほうに向き直ると美しい顔のまま、後ろに積み上げられた大きな座布団にもたれかかって眠っていた。
寅吉は前で組まれた白い手を握ってみようと自分の手を伸ばした。
「ぎゃあ」
声にならない声をあげたのは花嫁ではなく清吉のほうである。
その白い手は氷のように冷たかった。
花嫁は死んでいたのである。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。