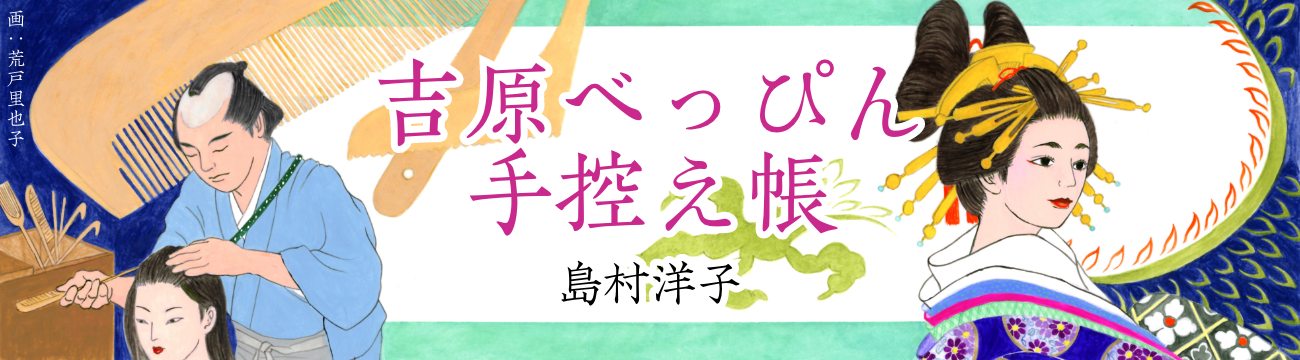第三話 絵馬の花嫁
島村洋子Yoko Shimamura
八
「花魁、加減はどうだい?」
という声で目が覚めた龍田川は、夢を見ていたことに気がついた。
大雪の晩に恐ろしい魔物に襲われそうになると必ず美しい女の人が守ってくれる夢を繰り返し見る。
それはどこかに封印されていて普段は出てこない自分の記憶かもしれないし、あるいは後から聞かされた話を勝手に物語にしたものなのか龍田川にはわからなかった。
しかし今回はいつも見る雪の日の夢以外にも不気味な光景を見た。
自分が渡っている橋の向こうにひょろっとした色の黒い若い男が立っていて、こちらに早く来いとでもいうように手招きをしているのだ。
全く話したこともない見覚えのない男である。
名も知らないその男のもとになぜか早く行かねばならない気がして夢の中の龍田川も足を早めるのだが、誰かが手を引っ張って止めようとする。
それを振り解(ほど)いてまた歩みを早めようとする時に、
「花魁、花魁」
と声がしたので目を開けたら二人の女が自分を覗(のぞ)き込んでいた。
遣り手ばばあのおきぬとお糸である。
おきぬは若き日には春日屋で女郎として働いていたのだが、その気働きと賢さで男相手の商売をやめるように店から言われ、その後は女郎たちの面倒や算盤(そろばん)から客引きまでなんでもござれで春日屋幸兵衛を支えていた。
幸兵衛の妾(めかけ)だったこともあるという噂もあったが、女将のお時ともうまくやっているところを見ると、それは間違っているのではないかと否定する噂もある。
もうひとりのお糸は最近、遣り手ばばあの仕事をやり出したのだが、おきぬについて歩いて見習いをしている。
いまはいろいろなことができるようになり、階段を上がって左の一津星のほうはお糸が、右側の龍田川のほうはおきぬが手分けして差配していた。
「あ、目が覚めましたね」
そう言っておきぬが龍田川をよっこいしょと抱き起こし、その背中をすかさずお糸が支えた。
「さあ、花魁、精のつく薬ですよ。両国まで買いにやった珍しいものなのでちゃんと食べないといけませんよ」
何やら葱とともに開いた魚の干物のような大きなものが皿に載っている。
見たことのないものだったが、焼いた味噌のうまそうな匂いに食欲はなかったがものは試しと食べる気になり、龍田川は箸を持った。
ひとつ小さな固まりを口にするとそれはとろけそうにうまかった。
驚いたことに龍田川は牡丹肉の焼いたものをぺろっと一人前食べたのである。
「おお、ようござんした」
おきぬがほっと息をついて喜んだので龍田川はそれほど自分のことを心配してくれていたのかと内心嬉しかった。
お糸とも目があったが気のせいかお糸は面白くなさそうな顔だったので、龍田川は獣を食う者を嫌がる者もやはりたくさんいるのだなとぼんやりしている頭で思った。
- プロフィール
-
島村洋子(しまむらようこ) 1964年大阪府生まれ。帝塚山学院短期大学卒業。1985年「独楽」で第6回コバルト・ノベル大賞を受賞し、作家デビュー。『家族善哉』『野球小僧』『バブルを抱きしめて』など著書多数。